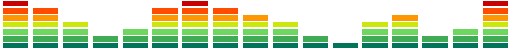
| Essay Sorry, Japanese ony.  ハーモニカ・トリオといえばハーモニキャッツです。たまたま米国の出張先の近くに最後のバス奏者だったDick Gardnerさんが住んでいたので、修理技術を教えてもらったり、彼等の演奏のテープ・コピーを頂いたりと幸運な経験をしました。その後、リードを吹いていたJerry Muradさんが亡くなり、助っ人やアレンジをしていたPete Pedersonさんも亡くなり、Dickさんが最後のHarmonicats Memberとなってしまいました。 私達のトリオ演奏でも、彼等の演奏を参考にさせていただいた曲がいくつもあります。 |
| 12番街のラグ(Twelfth Street Rag)♪ ラグタイム・ジャズの定番。原盤のLPの演奏ではハーモニカ・トリオに加えラグ・ピアノが加わっており、ご機嫌なプレイをしております。 途中にオクターブ奏法とその横滑らしトリルがいい味わいを出しています。また、アドリブ・フレーズが始まると、バス・ハーモニカがウォーキング・ランを始めますが、これはノリノリの演奏で、もう、バス・ハーモニカを吹いているだけで楽しくて仕方ないといった趣になります。最後に倍テンポの部分が出てきて、ここはクロマチックの活躍どころ。どころ。ただし、かなり難しい。特に、速いフレーズのコード・ハーモニカの後打ちリズムをピッタリ合わせられるようになれば素晴らしい演奏になります。 |
| センチメンタル・ジャーニー(Sentimental Journey)♪ 原曲はスローなムードたっぷりの演奏ですが、ハーモニカキャッツの演奏は大変速くてリズミカルなものです。全体がDb調で装飾音符が付けやすくなっています。また、3度奏法とオクターブ奏法を使い分け、重音でも音が濁らないように巧みなアレンジがされています。途中のアドリブ・フレーズはシンコペーション一色。しっかりしたリズム感が要求されます。 なお、この曲はクロマチックだけで吹いても音が重厚で十分聞き応えがあるために、宴会などで演奏を要請されたときに吹くにはとてもいい曲です。アメリカでDickさんと出会ったときにこの曲を吹いたら、すかさずDickさんがバスを付けてくれたこと、なつかしい思い出です。そのときはこちらが途中でコケてしまったのですが、Dickさんだけ最後まで吹き終わりました。またイギリスのミレニアム国際ハーモニカフェスティバルで吹いたときはアメリカのコード奏者がその場で暗譜でバックを付けてくれました。 |
| 慕情(Love Is A Many Splendored Thing)♪ 映画「慕情」のテーマ。Harmonicatsの演奏はスローでのびのびとした演奏です。で、一見簡単そうに思えるのですがどうしてどうして。 まず、クロマチック奏者がマスターしておくべき調子であるBbmの曲であるために、bが5個付きます。Bbmや長調のDbの楽譜を読み慣れている人にとっては大したことはないのですが、初めてb5個の楽譜を見る人にとってはとても読みにくいと感じられるでしょう。 次にコード・ハーモニカはスローの流しを聞かせた吹き方で、あのザー、ザーとした感じを出すのが中々大変です。 バス・ハーモニカの場合は最初と最後に半音階進行が出てきて、それが16分音符なのでこれまた大変です。口の中を切ってしまうことがよくあります。でも、おかげで半音階進行に強くなれます。 なぜ、この曲の演奏にBbmという調子を選んだのでしょうか?途中で確かにいくつかの半音下からの装飾音符が出てきますが、それほど必然的なものとも思われないのですが。考えられることは、BbmではなくA#mの曲として#7個で書いてあるのかもしれません。そうであれば、この調子は米国ではごく普通に採用される調子なのかもしれません。イギリスで出会ったアメリカ人の演奏を聞いていると、たしかにBbmとかDbの曲が多かった印象があります。 |
| ラスト・アウトポスト(The Last Outpost)♪ Harmonicatsの軽快な行進曲。Pete Pedersenの編曲です。サンプルでは表現し切れなかったのですが、最高音の吹音を滑らせる装飾音符がすごく格好よく、また最高音であるがために力むと音が出なくなりますので、うまく力を抜いて高音部を鳴らす呼吸の練習にはもってこいです。 しかし、その後次々に襲ってくる転調の嵐は、クロマチック奏者泣かせです。0->1b->6b->1#->4b->0と転調します。F調からはGb調、G調、Ab調と半音ずつ高くなっていくのですね。似たような転調をする曲には他に「マック・ザ・ナイフ」がありました。このような曲が吹けるようになれば、ぐっとクロマチックの実力がアップします。 なんどか練習を試みていたのですが、当時子供向けの丁度いい出番がなく、そうこうしているうち仕上がらないままグループが解散してしまい、人前で吹いたことはありません。個人的にはとても吹きたい曲の一つです。ぜひ、人前でカラオケで吹いてみたいものです。 |

トップページへもどる