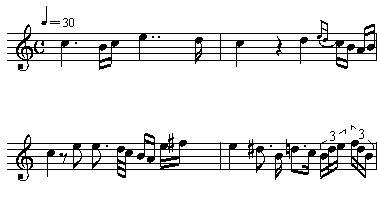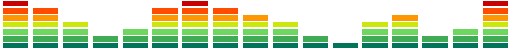
複音奏者のためのクロマチック入門(7)
スロート・ビブラート スロートというのは喉のことです。スロート・ビブラートでは喉の震えを利用します。 ウッ、ウッ、ウッ、ウッ、ウッという感じで喉で息を切るようにすると、滑らかでない、かすれたようなビブラートがかかります。息を切るといっても本当に切ると音が途切れてしまいますから程度問題なのですが、色々工夫してみてください。これまた、西部劇の映画で流れるようなとてもハーモニカらしいビブラートが得られます。日本の曲でしたら、「時には母のない子のように」などがこの吹き方にぴったりだと思います。 次に示すのは、「時には母のない子のように」の前奏部分です。森本恵夫先生のクロマチック・ハーモニカの音色は素晴しかったですね。bが2個のGm調の曲です。B音とE音にフラットが付き、それぞれBb音とEb音になりますが、前奏ではBb音しか出てきませんので、簡単に吹けると思います。 |
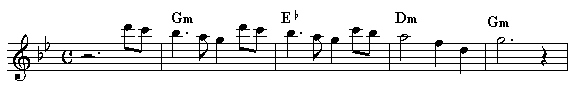
トップページへもどる |
お話へもどる |
入門6へ |
入門8へ |