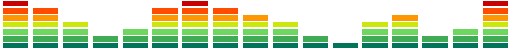
複音奏者のためのクロマチック入門(6)
ビブラートのいろいろ 特にハーモニカでなくてもいいのですが、音楽のCDを聴いているとどんな楽器や声楽でも必ずといっていいほどビブラートがかかっています。ビブラートのかかっていない音は実につまらないものです。 複音ハーモニカは2枚のリードのかすかな音程の違いにより、自動的にビブラートがかかるという特性を持っています。息の具合を調節して、耳に快いビブラートが響いてくる吹き方をすると、とても感じのよい音になりますね。 ところがクロマチック・ハーモニカは生憎1枚のリードで音を出す単音楽器です。複音のように自動的にビブラートがかかるということはありません。自分の技量でビブラートをかけなくてはならないのです。 クロマチック・ハーモニカのビブラートのかけ方には、次のような方法があります。 ・ ハンド・カバー奏法 ・ 手の動きを利用するハンド・ビブラート ・ 喉の動きを利用するスロート・ビブラート ・ 横隔膜の動きを利用する横隔膜ビブラート ・ 顎の動きを利用する顎ビブラート ・ 舌の動きを利用するタング・ビブラート これらをすべてマスターする必要はないでしょうが、いくつかができるようになっていると、曲によって、あるいは1曲の部分によって使い分けることにより、非常によい効果を生み出したり、変化を付けて演奏が単調になるのを防ぐことができます。 ハンド・カバー奏法 これについては前回説明しました。これぞハーモニカといった独特の音色が出せますから、ぜひマスターしておきましょう。 ハンド・ビブラート バイオリン奏者やチェロ奏者の演奏がテレビでクローズアップされると気付くと思いますが、左手が盛んに動いています。クロマチック・ハーモニカの場合には、ハーモニカを持つ手を前後に動かします。両手を同時に前後に動かすとよい効果が得られるはずです。バイオリン奏者を観察すればよくわかりますが、いつも手が動いているわけではありません。細かな音の動きでは手を動かす必要はなく、音が伸びるところでビブラートをかけています。クロマチック・ハーモニカの場合もロング・トーンのところで手を動かせば十分です。 注意事項が二つあります。一つは、手が動いているということとビブラートがかかっているということを混同しないでほしいということです。私の学生時代の経験ですが、手を盛んに動かしているにも関わらず、録音テープで聞くとちっともビブラートがかかっていませんでした。これを防ぐためには、吹きながら必ず耳でビブラートを確認することが必要です。 もう一つは、音程を下げた吹き方をしないということです。複音の「荒城の月」でもバイオリン奏法の部分でこの奏法が出てきますが、佐藤先生が音程を下げてはいけないと注意してあるにも関わらず、下げて吹く人がいます。吹いている人は感じがよいと思ってやっているようですが、聞く方からすると前の部分と音程が変わるのがわかって、とても感じの悪いものです。クロマチック・ハーモニカの場合はほとんど伴奏付きで演奏されるので、音程が下がるというのは致命傷的な悪い効果が出ます。 このビブラートは、バイオリン的な効果を出すときによく使います。ビブラートの速さは手でコントロールできるので、他のビブラートより細かなビブラートが可能です。吹き吸いをコントロールしてバイオリンの弓が静止から動きへ移る感じを出すと、よりバイオリン的な音が得られます。4オクターブの低音部で使うと、チェロ的な効果も出すことができます。チェロのビブラートはバイオリンより遅い動きであることにも注意しましょう。 また呼吸の加減ではバイオリンではなく、とてもハーモニカらしいビブラートも作り出せます。とても綺麗なハーモニカ的ビブラートをかける先生をよく観察していましたら手が動いていたので、試して見るとよく似た音を作ることができました。このように他の人の演奏を観察することも自分の技量を上げるよい方法ですので、ぜひ実践して見ましょう。 |
トップページへもどる |
お話へもどる |
入門5へ |
入門7へ |