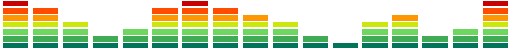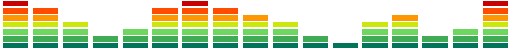複音奏者のためのクロマチック入門(8)
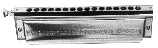
顎ビブラート
顎を動かすというか、口をパクパクさせるというかすると、顎ビブラートがかかります。横隔膜ビブラートというのは、かかり始めると弾みがついてかかり続けるのですが、中々かかり始めません。そんなとき、顎を動かして横隔膜ビブラートがかかるきっかけを作ってやるといいのです。
最初クロード・ガーデンさんから横隔膜ビブラートを教わったときに、中々かからないので、さらにガーデンさんの演奏を観察していました。すると、顎が動いていることに気が付きました。ガーデンさんに指摘すると、本当?と聞き返してきたくらいで、本人は意識していなかったようです。
それ以来、顎を動かす練習をしましたが、以外に等感覚で顎を動かすというのは大変なもので、安定した動きができるようになるまでには数ヶ月かかりました。
慣れると、単に横隔膜ビブラートのきっかけだけでなく、顎ビブラートそのものもいい感じのビブラートになることが実感されました。それで、日によって横隔膜ビブラートがかかりにくいことがあるのですが、そんなとき顎ビブラートを多用することがあります。
次に示すのはガーデンさんが吹いた「Greensleeves」ので出だしの部分です。bが2個のGm調の曲ですが、Eb音には常にナチュラル記号が付くので、実質的にはbが1個の曲のように吹けます。装飾音符の好例でもありますが、ビブラートも素晴らしいものです。横隔膜ビブラートがかかりにくいようでしたら、顎を動かして弾みを付けてみてください。
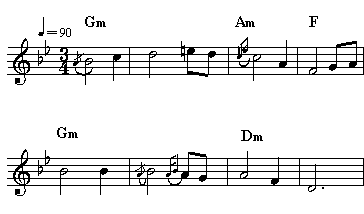
タング・ビブラート
タングというのは舌ですね。舌をイヨイヨイヨイヨという感じで動かすと、タング・ビブラートとなります。ただし難しいのは、このイヨイヨイヨイヨが大げさであると、聞いている人にもイヨイヨイヨイヨが感じられてしまって、とても優雅なビブラートにはならないということです。イヨイヨイヨイヨと舌を動かしながらイヨイヨイヨイヨを感じさせない動きにする、そこにコツがあります。
この奏法の名手はラリー・アドラー(故人)さんです。アドラーさんが初来日したとき、聴衆からは「幻のビブラート」といわれたと聞いたことがあります。1995年の横浜大会では実際にアドラーさんの演奏を聞くことができました。アドラーさん自身のおことばでは、オクターブ奏法をする場合には舌が使えないので、ハンド・カバー奏法でビブラートをかけるということです。
アドラーさんのCDは今ではたくさん販売されていますが、私は昔45回転シングル盤で聞いた「哀愁のエルサレム」という曲が大好きです。最近、CDに収録されたものも入手しました。
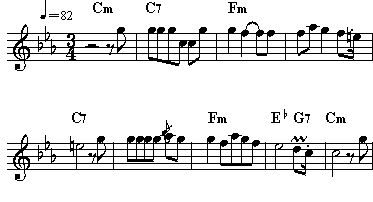
さて、いろいろなビブラートを紹介してきましたが、ビブラートができるようになることの効用は、人前でスローな曲が吹けるようになることです。若いうちは早い曲を「どうだ、こんなの吹けるのだぞと」とばかりに吹くことが多い(私もそうだった)のですが、ビブラートができるようになってからは、スローな曲を吹くのがとても楽しくなってきました。
映画音楽で流れるハーモニカ、例えば「ムーン・リバー」なんかはスローなとてもいい曲ですね。これが、譜面的には簡単なんだけれど、ビブラートができなかったころは様にならなくて、人前で吹くなんてことはとてもできませんでした。今は違います。スローな曲でもどんどん取り入れ、早い曲、スローな曲を織り交ぜてプログラムを作ることができます。
クロマチック・ハーモニカのビブラートには色んな種類があり、奏者によってハーモニカの音色が全く異なります。色んなCDやLPを聞き、気に入った奏者を参考にして自分なりの音色を作っていく、クロマチック・ハーモニカは奥の深い、とっても魅力的な楽器なんですね。
|