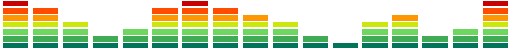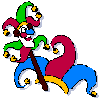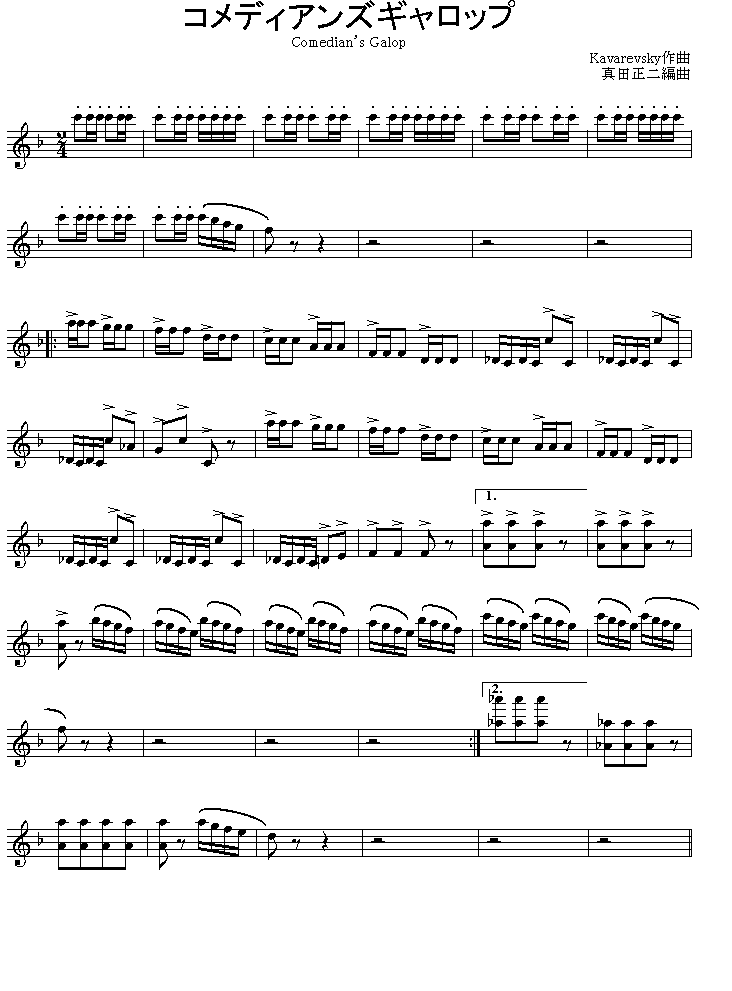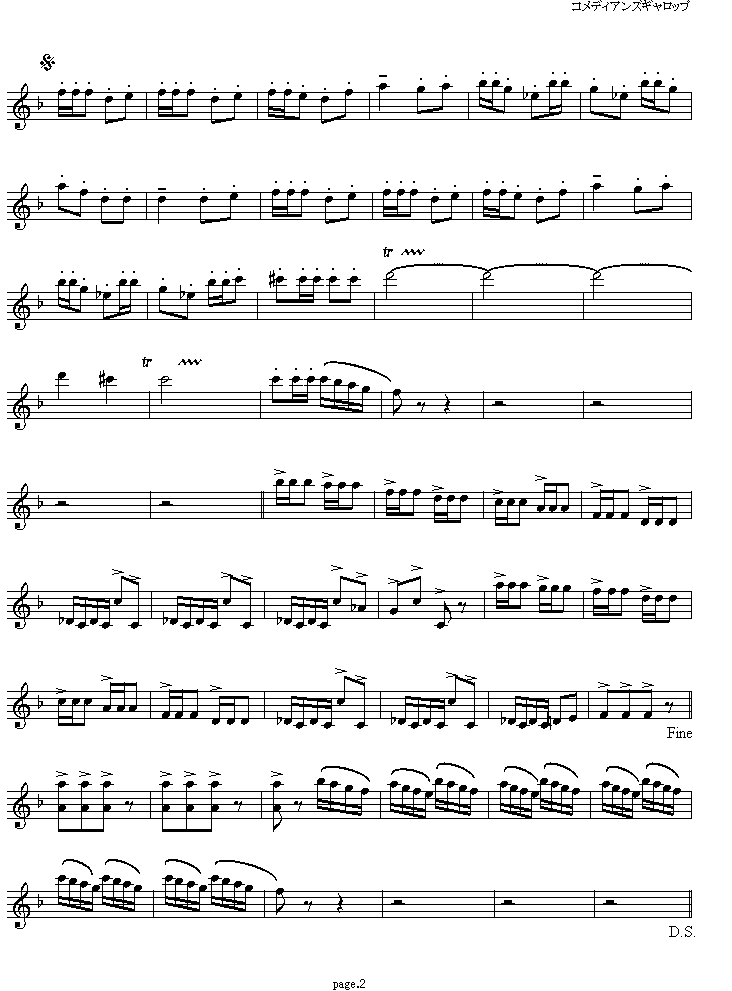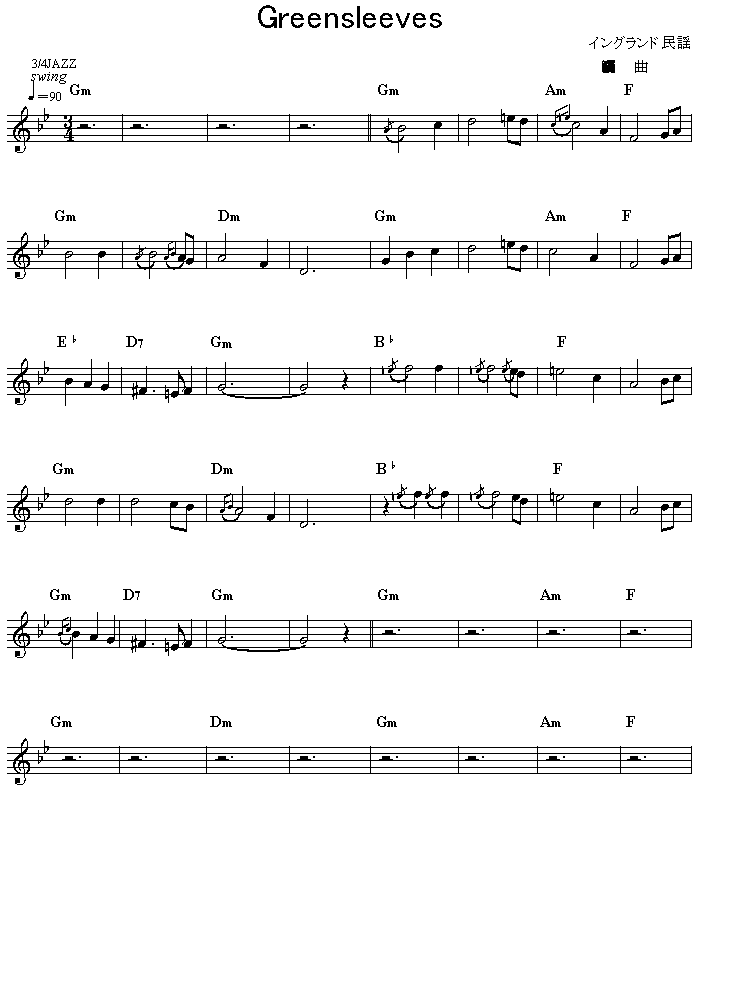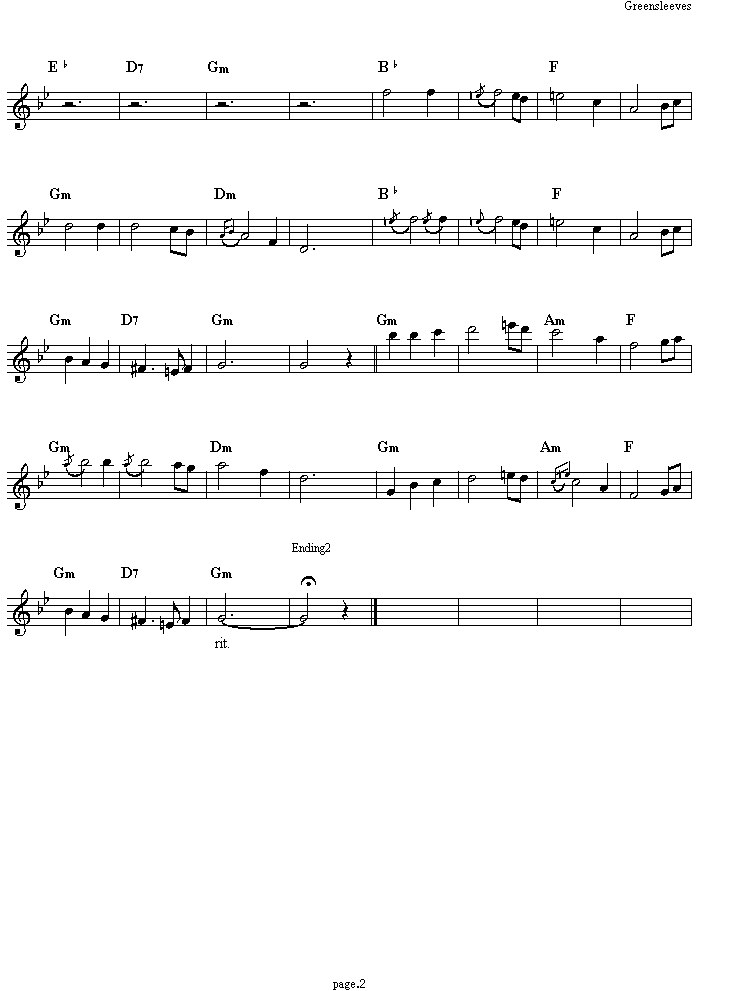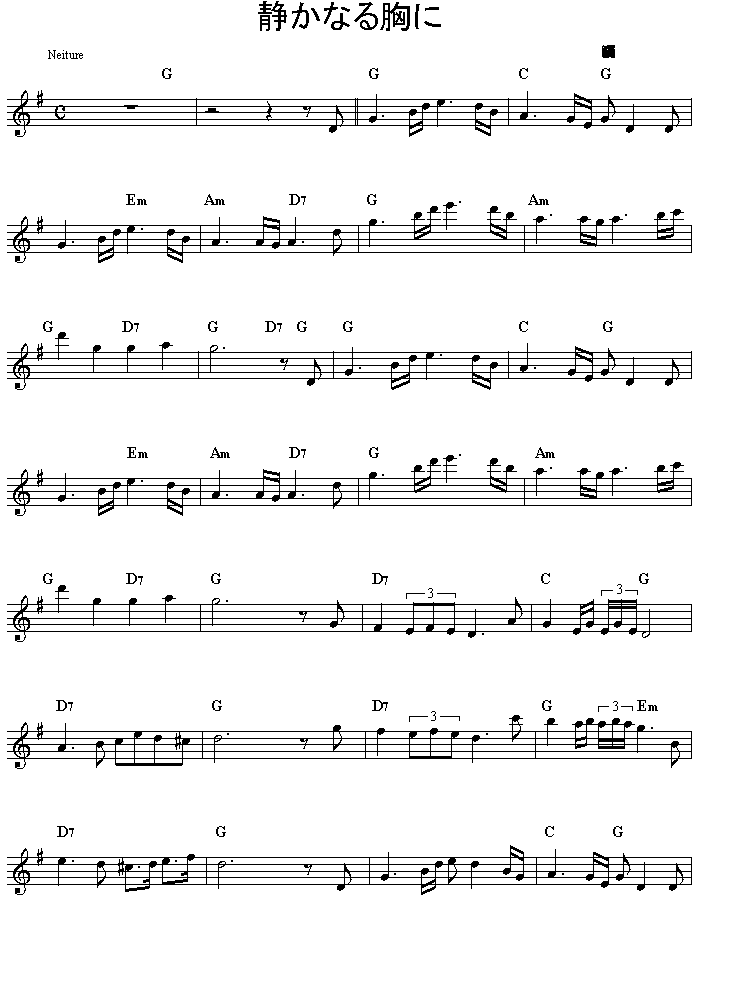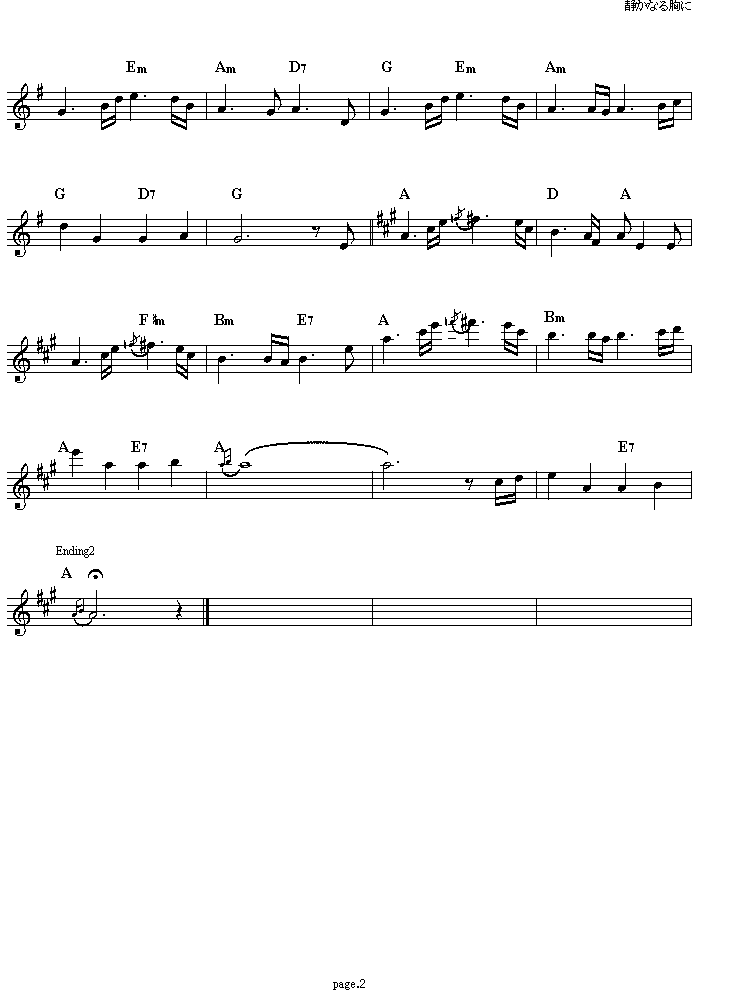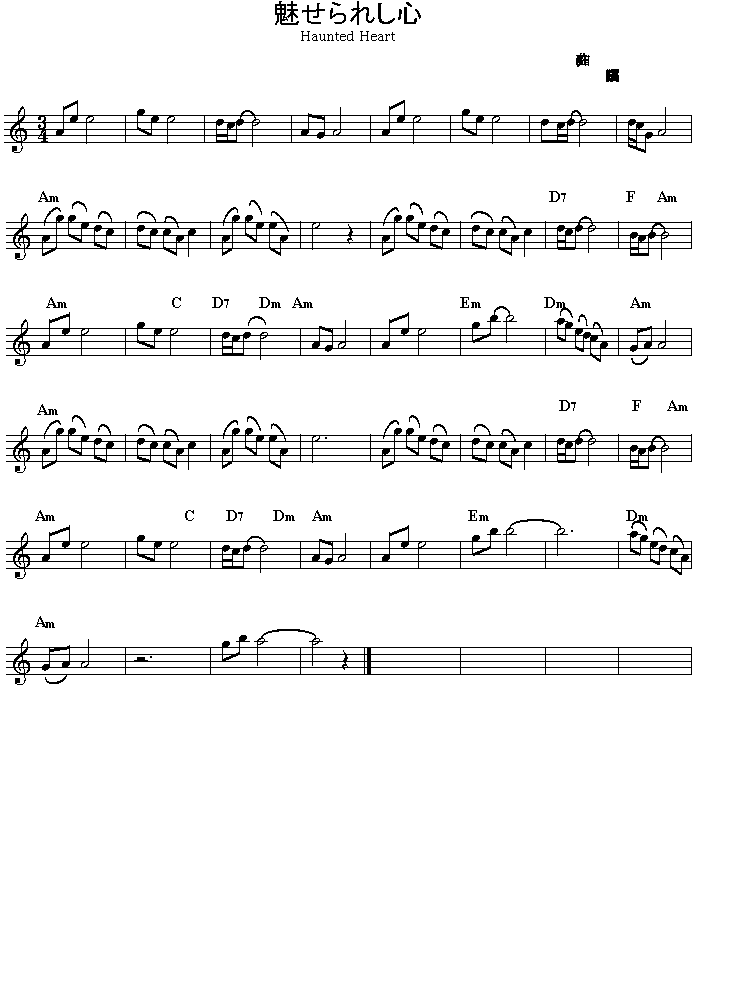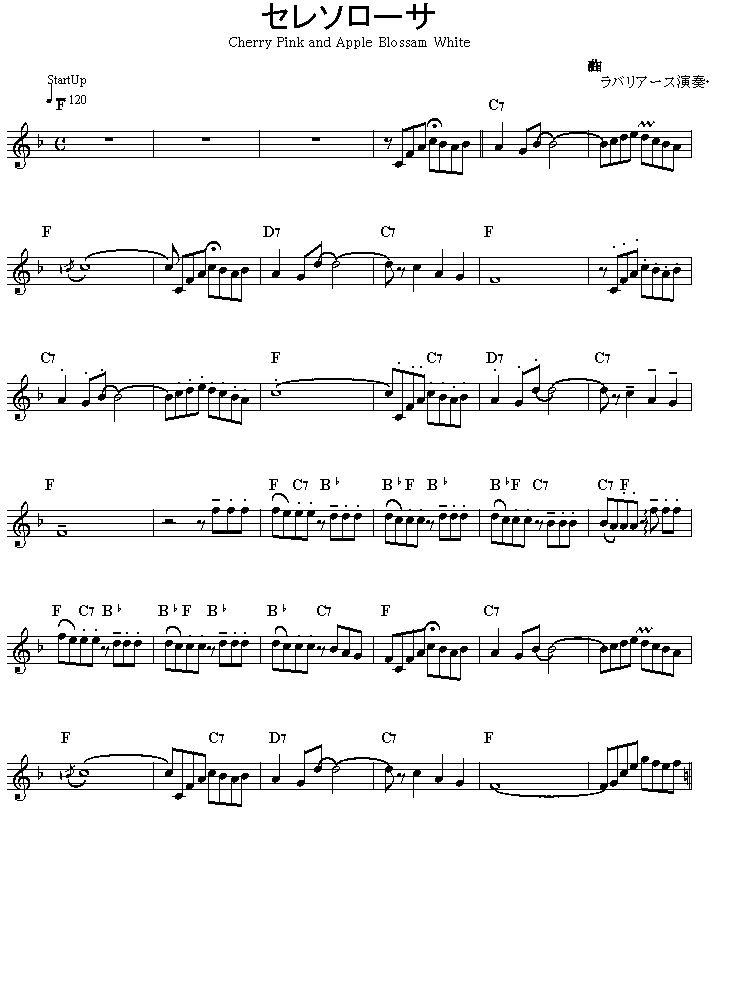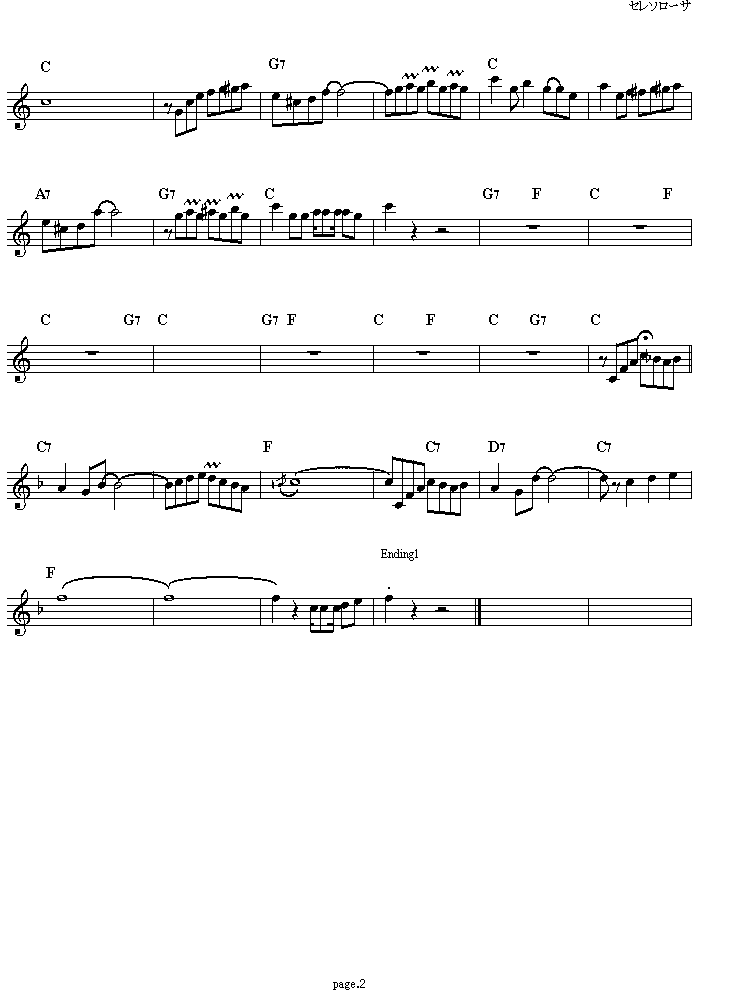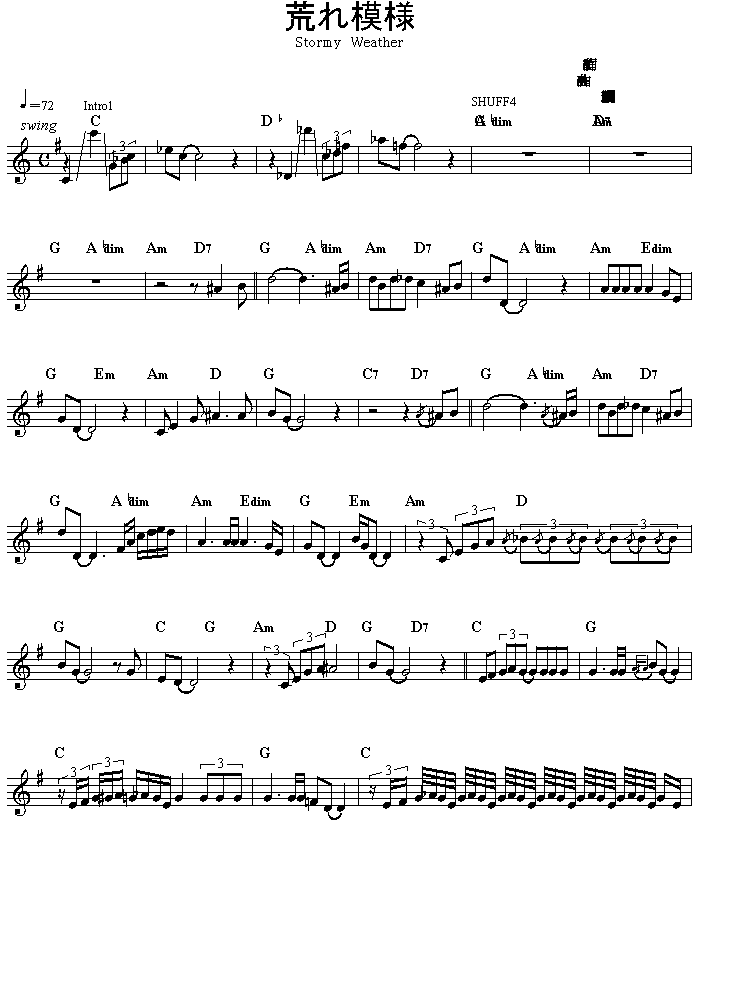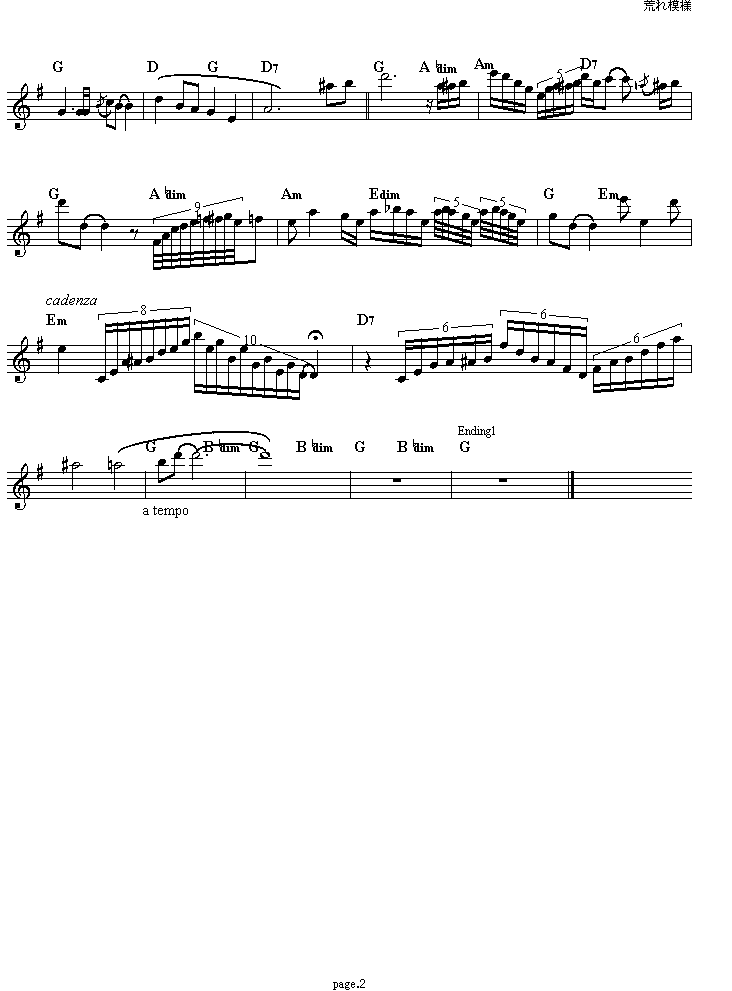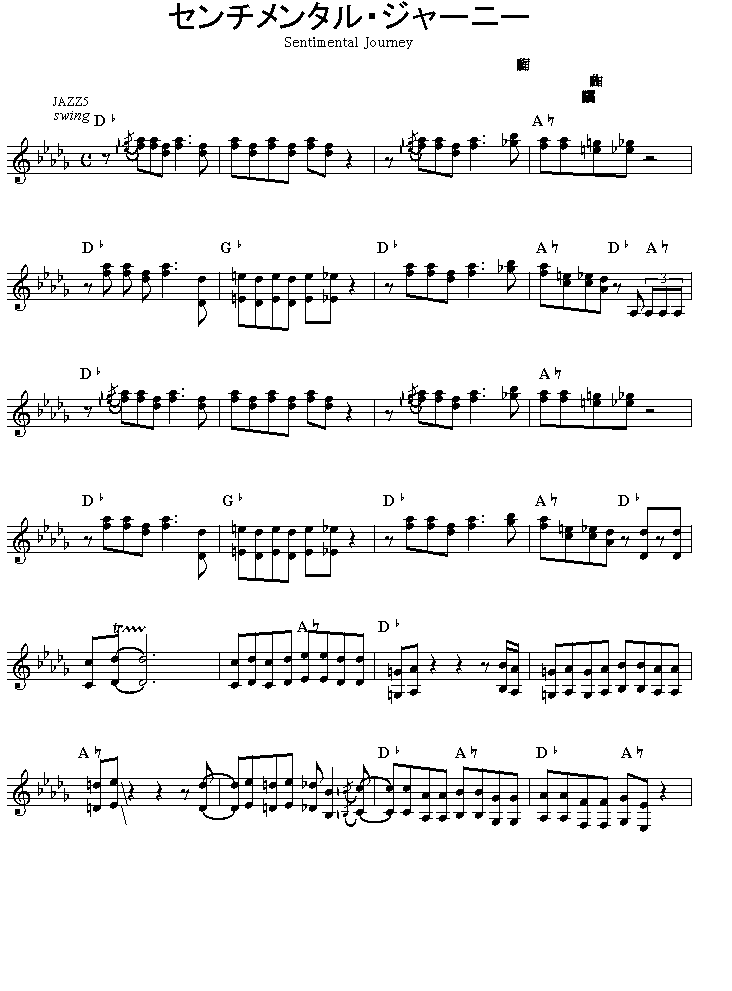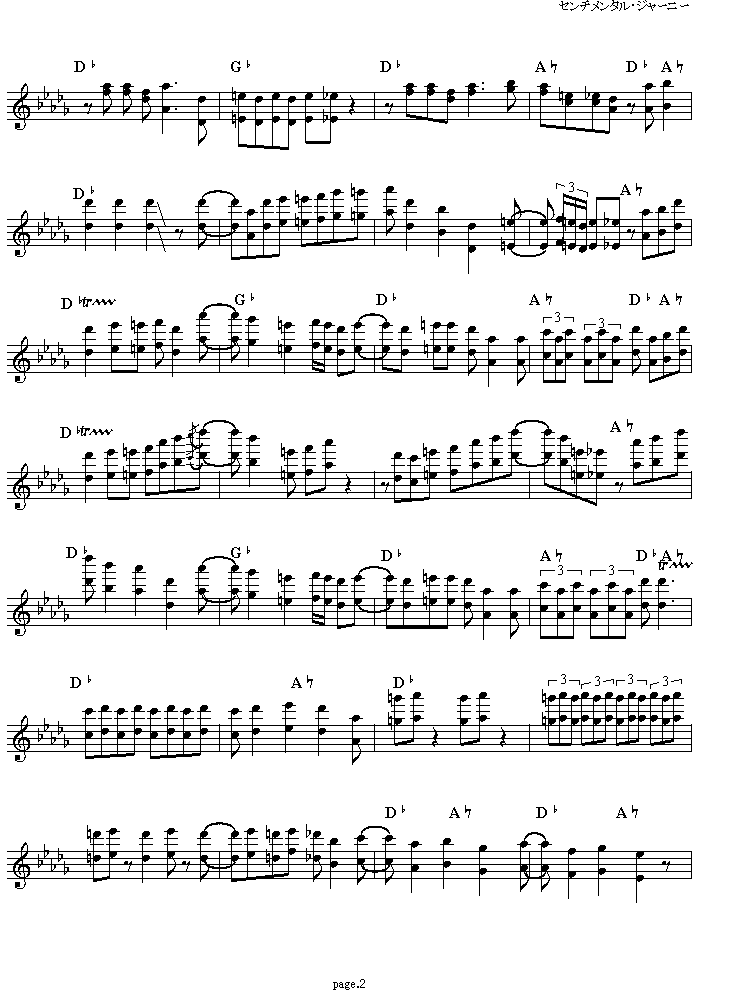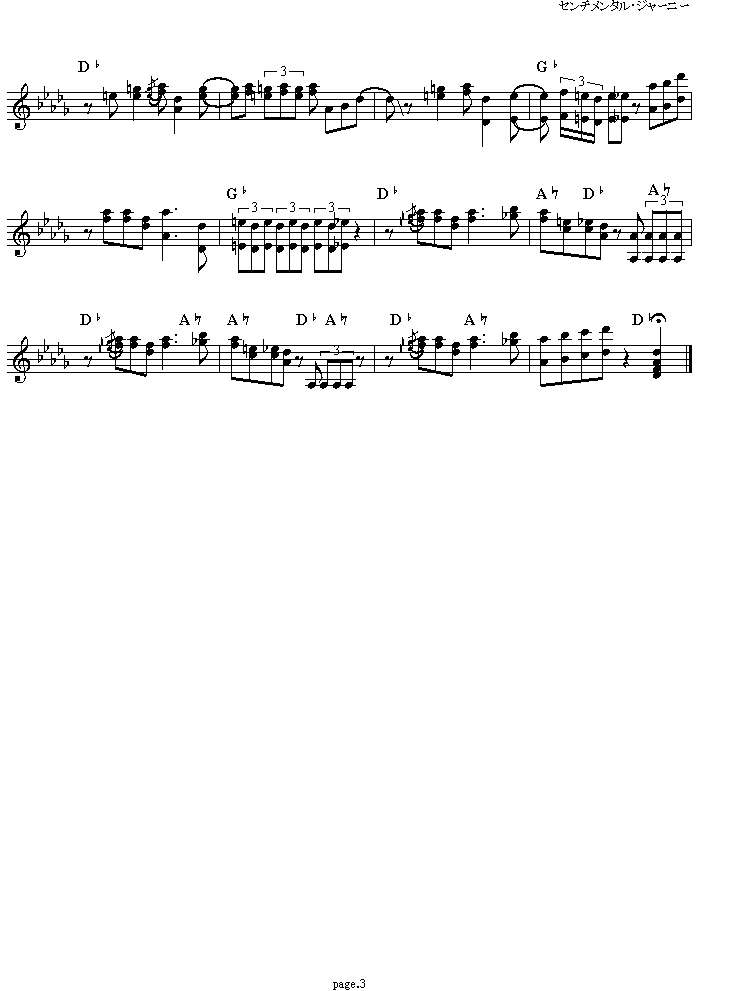巨匠たちに学ぶハーモニカ・テクニック

1998年6月20日、日本ハーモニカ芸術協会第189回実験工房で発表。
目次
1.コメディアンズ・ギャロップ
2.グリーン・スリーブス
3.静かなる胸に
4.魅せられし心
5.セレソローサ
6.ストーミー・ウェザー
7.センチメンタル・ジャーニー
1.コメディアンズ・ギャロップ 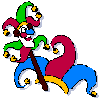
この曲はハーモニキャッツの演奏で有名ですが、日本でもいろいろなハーモニカ・トリオが同様のアレンジでレパートリーにしています。元々はカバレフスキー作曲のクラシックの曲で、道化師の楽しい踊りを描写した曲でしょう。運動会で聞いたことがあるかもしれませんね。ハーモニキャッツの古い演奏はクラシックのオリジナルに忠実な編曲で、後期のものがよく聞かれる現在の姿に進化したと思われます。
ここでの練習テーマは、速い曲に慣れるということです。速い曲で練習しておけば、普通の速さあるいは遅い曲での余裕が生まれるというものです。そういった、副次的な意味を込めての練習ですから、この曲自体が完成しなくても嘆く必要はありません。速い曲ではダブル・タンギングを使う場面が出て来ますが、ハーモニカの音は微妙なので舌の動きが音として聴衆に聞こえてしまいます。そこを工夫して、聞く人にバカにされないよう心がけるのも重要なテーマです。
◆速さに慣れる
- 中々完成しないでしょう
- でも、練習を続けることにより、速さに対する恐怖、あきらめがなくなります
◆速さのリズムを狂わさない
- 途中、とっても難しいところがありますが、そこでリズムを狂わさないようにしましょう
- 正確にできなくても、速さは保ちましょう
- 音符に正確で速さが狂うより、速さが正確で音符が不正確の方が、経験上うまく聞こえます
◆スタッカートに慣れる
- TKTK奏法ですが、TUKUTU TUKUTU よりはTAKATA TAKATA というつもりで、舌の音をさせないよう、いろいろ工夫しましょう
◆トリルに慣れる
- クロマチック・ハーモニカでよかったなあと思うのは、かっこいいトリルに出会ったときです
- 十分音をのばして楽しんで吹きましょう
◆暗譜する
- 速い曲を、楽譜に頼って吹くのはつらいものです
- 覚えやすい曲ですので、暗譜してしまいましょう
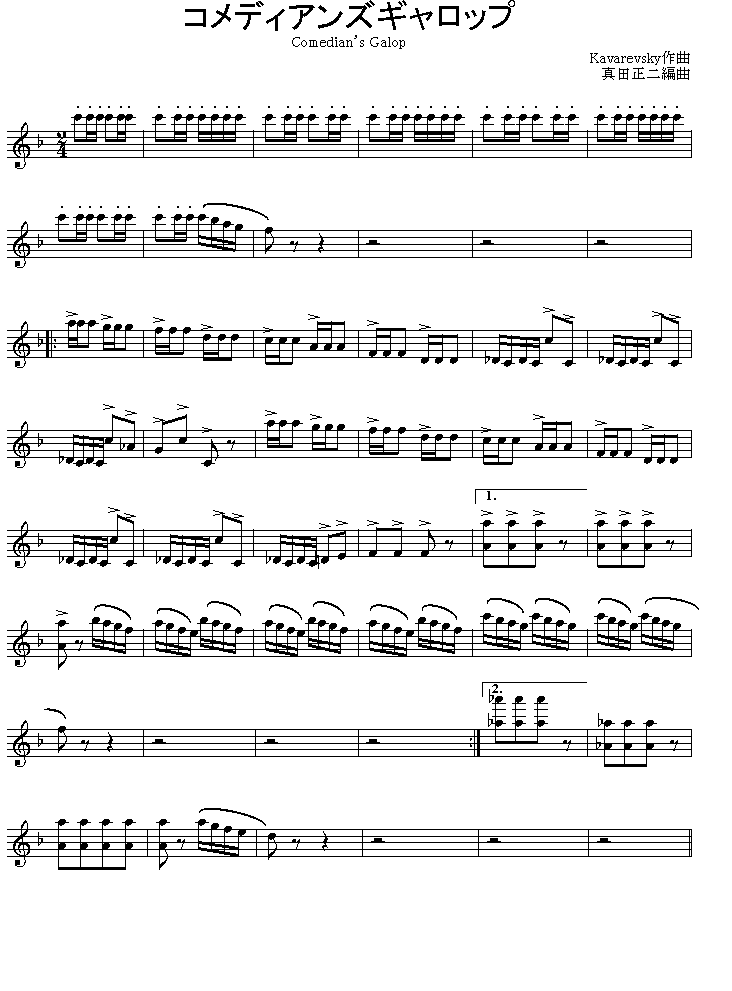
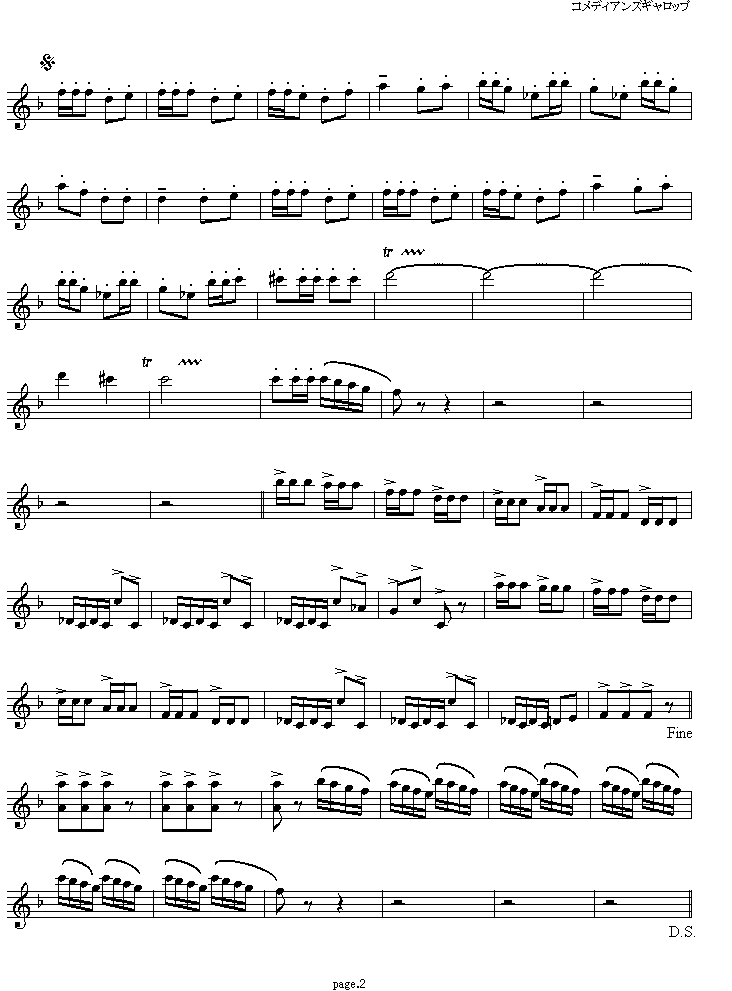
目次へ
2.グリーン・スリーブス
クロマチック・ハーモニカの装飾音は、管楽器のようにどのような組み合わせでもできるというものではありません。ごく限られた組み合わせが可能です。しかし、ボタン操作による装飾音は、他の楽器に見られない鋭いアタック感があり、とても魅力的なものです。この曲はクロード・ガ-デンさんが演奏しているものですが、b
2個のGmの調子を使い、装飾音が使える場所がAmのときより増えています。その使い方をよく習得して、他の曲でも装飾音を使えるようにしましょう。
ただし、ある組み合わせの場合に装飾音が使えるからといって、その組み合わせの場合いつでも装飾音を入れたりすると、聞く人からするとつまらなく聞こえてしまいます。その点、クロードさんは巧みに装飾音を入れる場所や種類を変えているので、大変参考になると思います。
サンプル試聴のページでMIDIですが出だしを聞くことガできますので雰囲気をつかんでください。また、伴奏も用意されています。
◆装飾音を使う
◆半音下からの装飾音
- b系の調子(F、Bb、Eb、Dm、Gm、Cmなど)は、半音下からの装飾音をつけやすいので、よく使われています
- E#(F)、B#(C)も利用すると、可能な装飾音が増えます
◆横に滑らす装飾音
◆装飾音で、リズムを乱されないように
- 指導した経験上、装飾音が出てくると、リズムを乱される初心者が多いようです
- 乱されないように、装飾音の感触に十分慣れておきましょう
◆使う場所に変化をつける
- メロディが繰り返される場合に、同じような場所で同じような装飾音をつけるのはやめましょう、聴衆が予測できてしまいます
- 意外性が聴衆を飽きさせないコツです
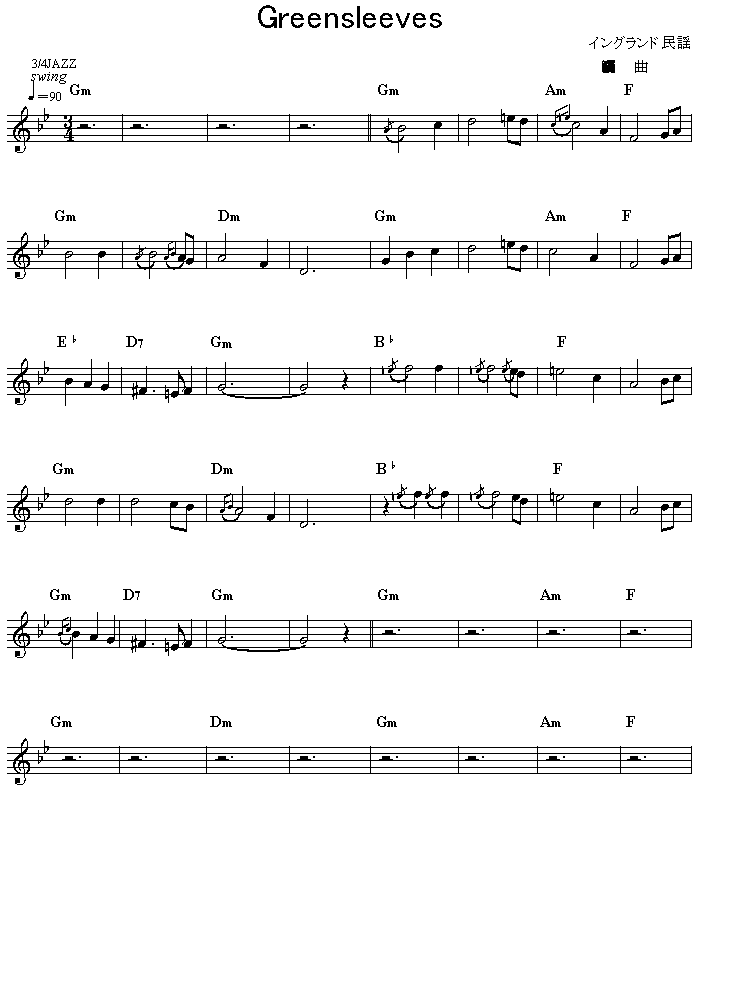
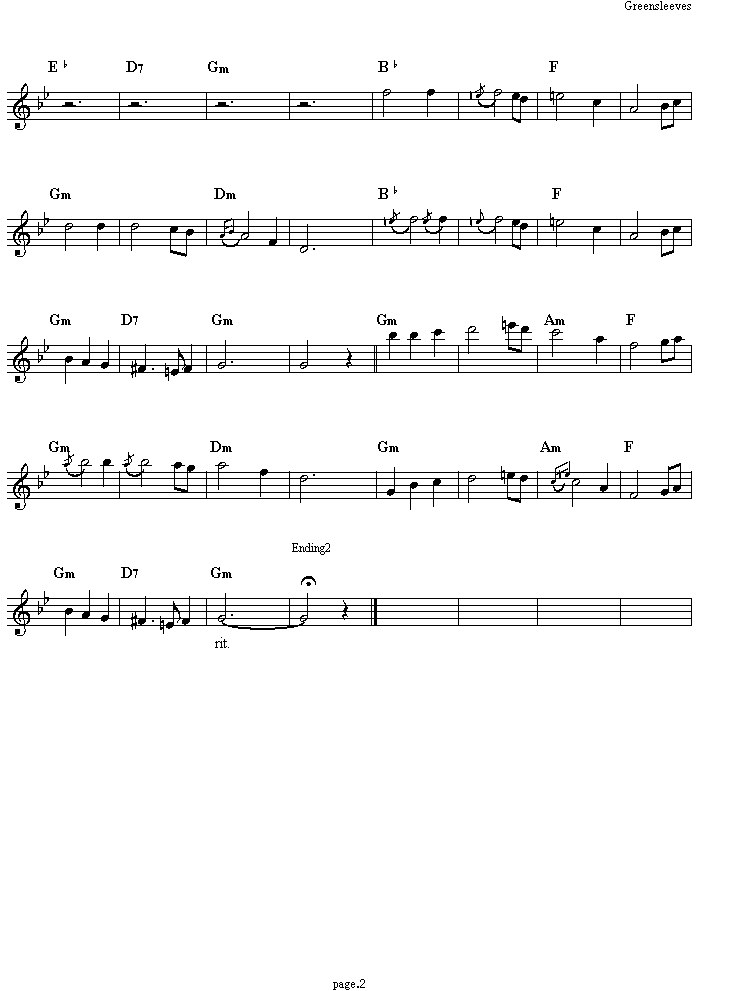
目次へ
3.静かなる胸に
唄と違って、ハーモニカの演奏で同じメロディを3題目、4題目と繰り返すと聴衆が飽きてしまいます。
途中にアドリブ部分を入れるというのがよい方法ですが、中々アドリブできるまでに上達するのは困難ですし、よいお手本を探してもなかなか見つけられません。
手軽に変化をつけるよい例がこの曲です。まずオクターブを変化させています。クロマチック・ハーモニカでは、オクターブが変わってもハーモニカの動きが変わらないので、10ホールズや複音に比べてこの変化は比較的簡単です。ただ、オクターブが変わると口の形も少し変えないといけないので、オクターブ間の移動は音階練習などを通して十分練習し、きれいな音が出せるようにしておきます。
もう一つの変化は転調することです。同じメロディを転調して吹くのは、初心者にとってはかなりつらいものがあるでしょう。しかし、それに慣れることがクロマチックを楽器として使いこなすためにどうしても必要なことです。まずは手始めにこの曲の転調方法を学びましょう。#
1個から# 3個への転調ですから、途中でメロディが1音だけ高くなる見本です。
◆オクターブの変化
- 同じメロディが繰り返される曲では、オクターブ違いの変化をつけて単調さを解消します
◆転調
◆転調の方法
- 1音高く − #が2個増えるかbが2個減ります
(C→D、E→F#、F→G、Eb→F、Am→Bmなど)
- 半音高く − #が7個増えるか、bが5個増えます
(C→C#(Db)、E→F、D→Eb、Am→Bbmなど)
- 5度高く − #が1個増えるか、bが1個減ります
(C→G、E→B、F→C、Eb→Bb、Am→Emなど)
- 4度高く − #が1個減るか、bが1個増えます
(C→F、E→A、F→Bb、Eb→Ab、Am→Dmなど)
◆クロード・ガーデンさん
- 何度も来日しているクロードさんの昔のレコードから、学ぶべき点がたくさんあります
- 音色の変化がすごい
- スピードがすごい
- 曲が洗練されている
- ジャズもクラシックも音楽はみんな好きだといっていました
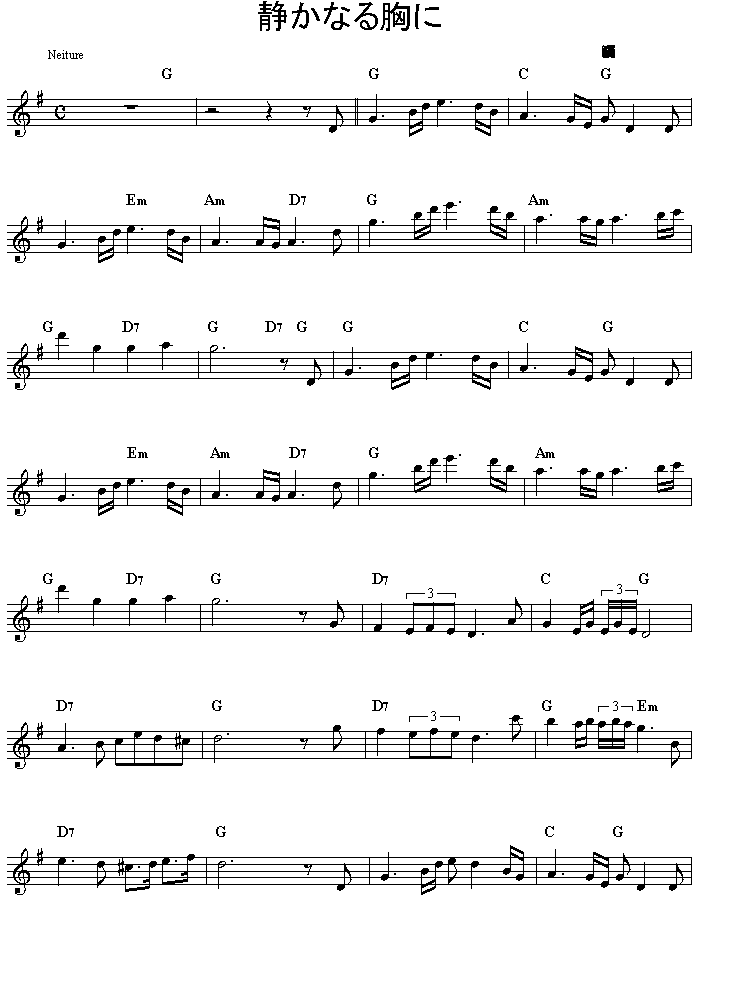
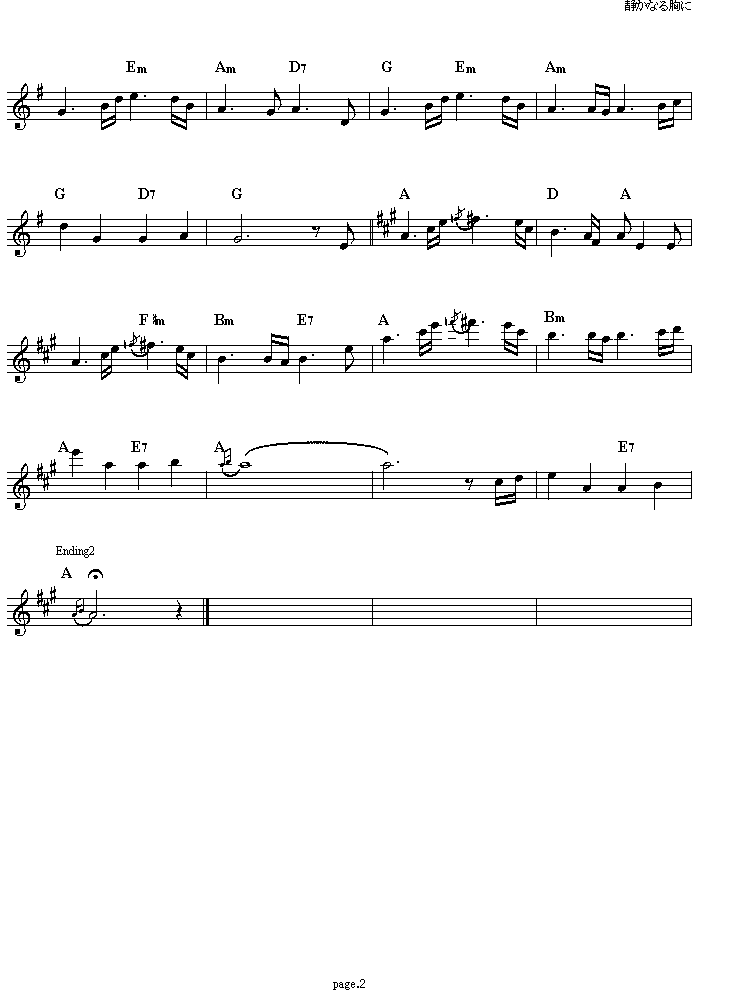
目次へ
4.魅せられし心
速い曲はとっても聴衆受けがしてレパートリに欠かせませんが、遅い曲を混ぜることによりこれがさらに効果を増します。ところが、スローな曲を感情を込めてきれいにきれいに吹くというのは決して簡単なことではありません。特にビブラートを使いこなせないと、本人はいくら感情を込めたつもりでも聴衆はそうと受け取ってくれません。速い曲が得意な人でも、スローな曲が苦手という人がたくさんいます。
この曲は演奏自体は簡単な曲ですから、感情を込め、ビブラートをかけて、聴衆を魅了できるような演奏を心がけましょう。この曲で人々を魅了できるようになれば、あなたのクロマチックは立派に1人前です。どんどんスローな曲をレパートリに取り入れることができるようになります。
ビブラートにはいろいろな種類があります。それぞれの曲に適したものを使い分けられるように練習しましょう。どの曲も同じビブラートというのでは飽きられてしまいます。
◆きれいに
- 単調な曲ですが、丁寧にきれいに吹きます
- いかにもハーモニカという音色を目指しましょう
◆ビブラートの変化
- メロディの変化に合わせて、ビブラートの質も変化させます
◆ビブラート
◆エディ・マンソンさん
- この曲を吹いていたエディ・マンソンさん(故人)は、たくさんの映画音楽を手がけました
- ミッチ・ミラー合唱団のハーモニカはこの人
- ムーン・リバーもこの人
- 他のラバリア−ズのレコードを持っている人はいませんか
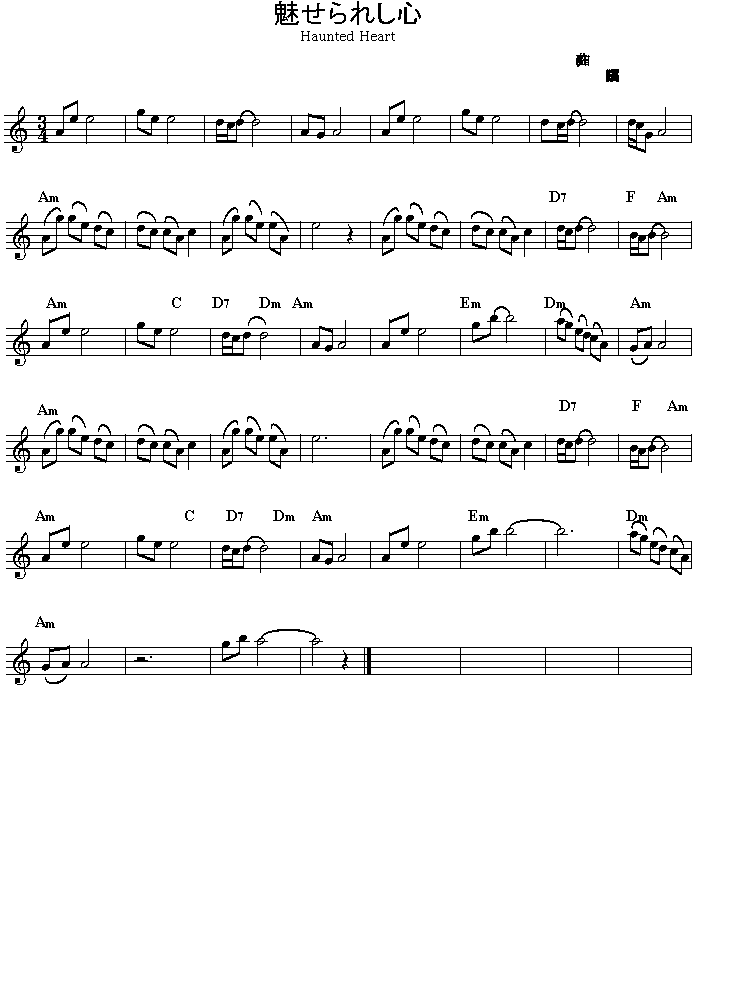
目次へ
5.セレソローサ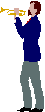
この曲はトランペットで演奏されることが多く、音の伸びているところで連続的に音を下げていき、そのまま今度は元の高さに戻すというテクニックが使われます。ここではそれをフェイクと呼ぶことにしますが、ハーモニカはフェイクが得意な楽器です。10ホールズではベンドは当たり前ですし、複音でも単音リード奏法を使えばフェイクが可能です。実際、複音でこの曲をレパートリにしている方がいます。ここではラバリアーズを参考にしています。
クロマチックでもよく使われる奏法です。ハーモニキャッツ、ラバリアーズなどの演奏があります。
口の中の形が「あーうーあー」といった具合に変化しますと、「うー」の部分で息の通り道が狭くなるため、音程が下がります。それを息をとぎらすことなく元の形に戻していくと元の音程に戻ります。
JAZZの世界では、下げて行くだけのフェイクがよく使われます。トゥーツ・シールマンスさんの演奏を聞くとこの効果がよく使われているのがわかります。口の中の形を変える練習をして、いろいろ試しましょう。たまに、下げ過ぎてリードを折ったという話を聞きますので、力まかせではなく、耳と口を連動させ、あくまで自分のコントロールの下にフェイクしましょう。
◆フェイク
- フェルマータでフェイクします
- 吹き方を変化させて音を下げます
- 頃合をみて、元に戻します
- よく耳で下げ具合を聞いて、リードを折らないようにしましょう
- 下げるだけのフェイクもあります
- 下げたところから元に戻して、上げたように聞かせる方法もあります
- 下げっぱなしでは、音が狂っているように聞こえますので、注意しましょう
◆スタッカート
- メロディをスタッカートで吹くところがあります
- 中々しゃれていますね
◆トリル、装飾音
- 瞬間的なトリル(wで表しています)が効果的です
- 半音下からの装飾音(B#を利用)、もうおわかりですね
◆テヌート、スタッカート、スラー
◆アドリブ
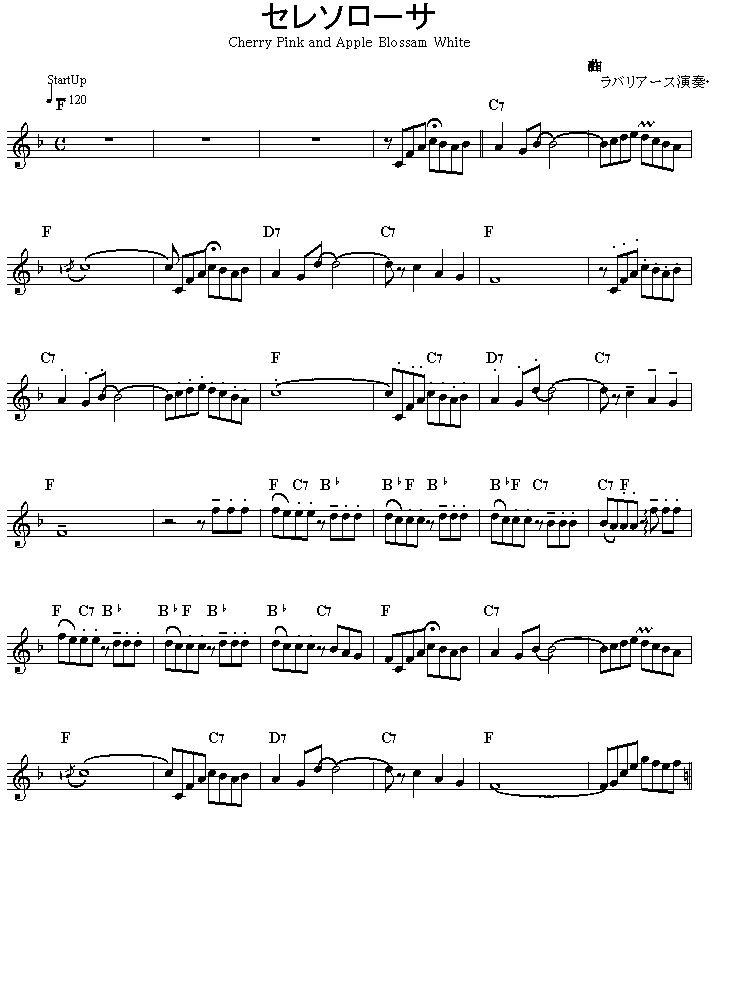
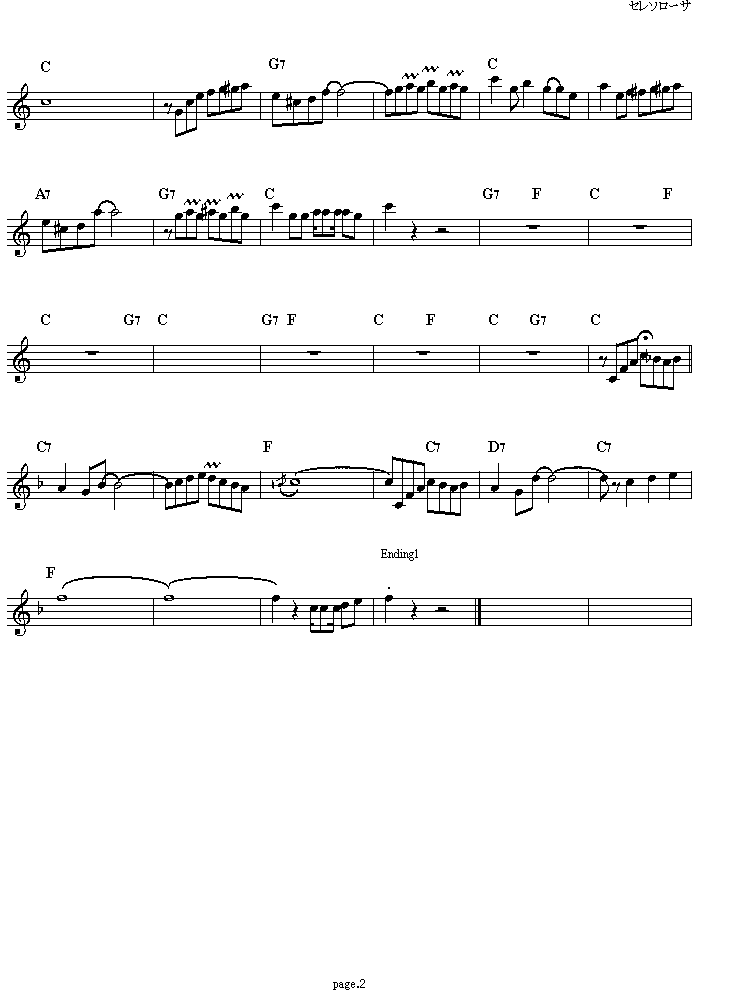
目次へ
6.ストーミー・ウェザー
ドイツ語のRの音を練習したことはありませんか。舌の先が震えてトゥルルという感じになります。
このラバリアーズの演奏では、スト-ミー・ウェザー(日本題 荒れ模様)の感じを出すために、前奏部分でこの奏法を使っています。吹く音に限られているのであまり使われませんが、有名な曲ではキャラバンのメロディが最初吹く音ばかりなので、クロード・ガーデンさんなんかがこの効果を取り入れています。
この曲は、その他に細かい音を小節の中にうまく収めて吹かなければならない課題があります。ボタン操作でできるので、そんなにむちゃくちゃ難しいわけではなく、中々楽しんで吹けます。
ラバリアーズの演奏を聞くと、スラーとかハンド・カバー奏法がうまく使われ、ぜひとも習得したくなってしまう1曲です。
◆Trrr
- 舌を使ってTrrrrrrrrと吹きます
- 吸えませんので、吹く音に限られます
◆装飾音、連符の使い方
- よく研究してみると、吹きやすいパターンを多用していることがわかります
◆スラーの効果
◆ハンド・カバー
- 途中で音色を変えるために使っています
- フェイクも使います
- 最後は、きれいなきれいなハンド・カバーのビブラートで終了しています
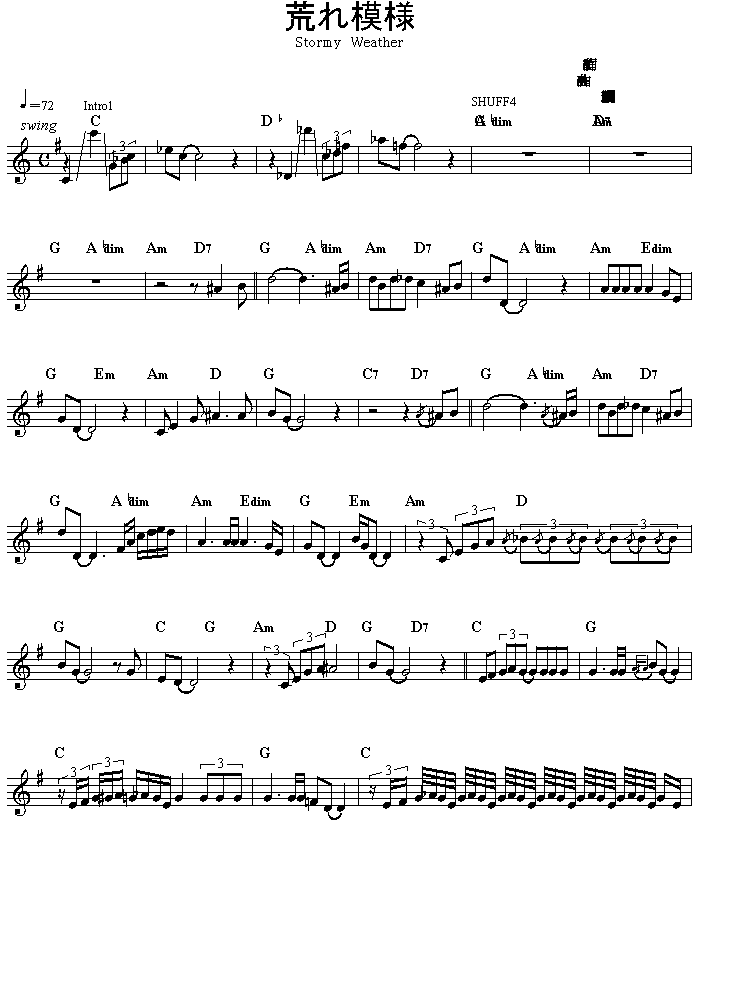
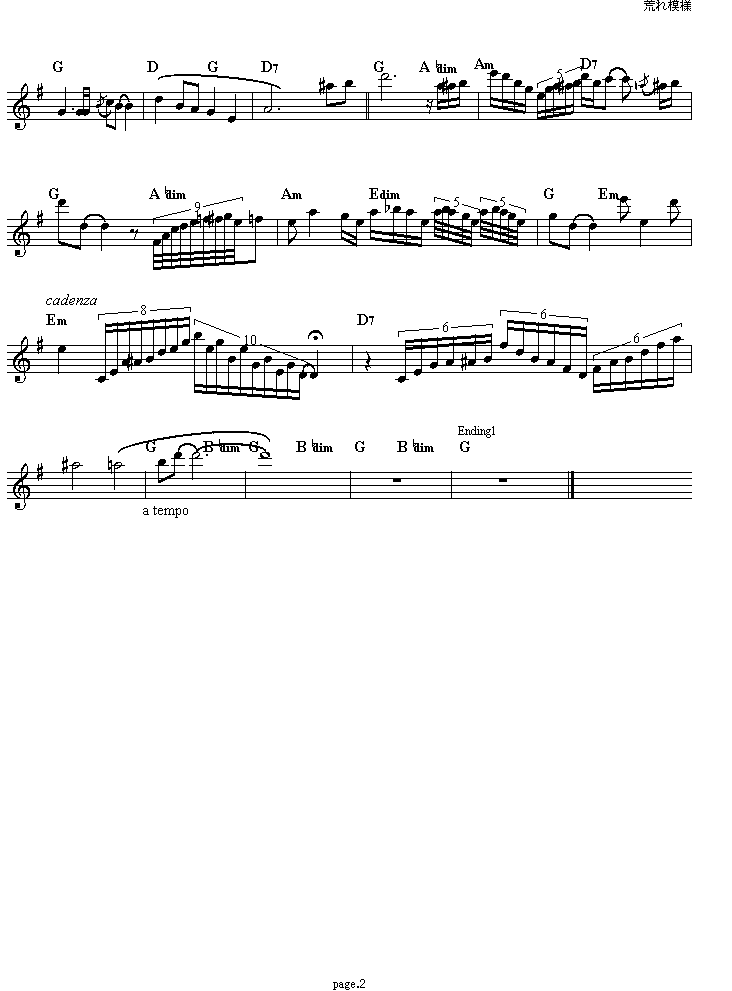
目次へ
7.センチメンタル・ジャーニー
ハーモニキャッツの得意曲の一つでしょう。
この曲はソロで吹いてもかっこいいため、宴会で演奏させられるときなんかに重宝します。
ハーモニカ界では、装飾音をどこにでもつけられるよう、Db(C#)調に編曲されることがよくあります。楽譜としては、C#調(#
7個)で書けばあまり問題なく読めるのですが、音楽界ではDb調(b が5個)として書くのが当たり前であるため、ここではDb調で書いています。したがって、楽譜を読みにくいと感じる方が多いと思いますが、クロマチックではよく使われる調子であるため、この曲で読み方を練習しておきましょう。
全体的に重音で演奏されます。3度奏法、オクターブ奏法をおりまぜ、非常にかっこいい演奏となりますが、その分、難しいので心してかかってください。
また、シンコペーションの連続ですから、伴奏に惑わされないようになっておくことも重要です。
オリジナルは感傷旅行という意味で、スローな曲ですが、ハーモニキャッツはアップ・テンポで演奏しています。この曲が演奏できれば、もう恐いものなしといってよいでしょう。がんばってください。
◆装飾音
- 半音下からの装飾音を使うために、C#(Db)の調子を使っています
- これなら、どの音にも装飾音を自由につけられますね
- bが5個なので、読譜が大変に思えますが、ハーモニカでよく出てきます
- 演奏が難しくなるわけではないので(#が2個は大変です)、この記法には慣れておきましょう
◆重音
- 3度と8度(オクターブ)を使い分けています
- 重音でも、これならきれいです
◆リズム感
- アドリブになると、シンコペーションがたくさん使われます
- リズム感をしっかり養成しないと、バックと合いません
- 基本的なシンコペーションの練習が必要です(ジャズの教則本には必ずでています、目を通して、練習しておきましょう)
◆ジェリー・ミュラッドさん
- ハーモニキャッツのメロディ奏者(故人)です
- ジャズ感覚の楽しい曲がいくつもあります
- メンバーのディック・ガードナーさんがこの曲のバスを吹いてくれました、楽しい想い出です
- 彼が、ムラッドでなくミュラッドと発音していました
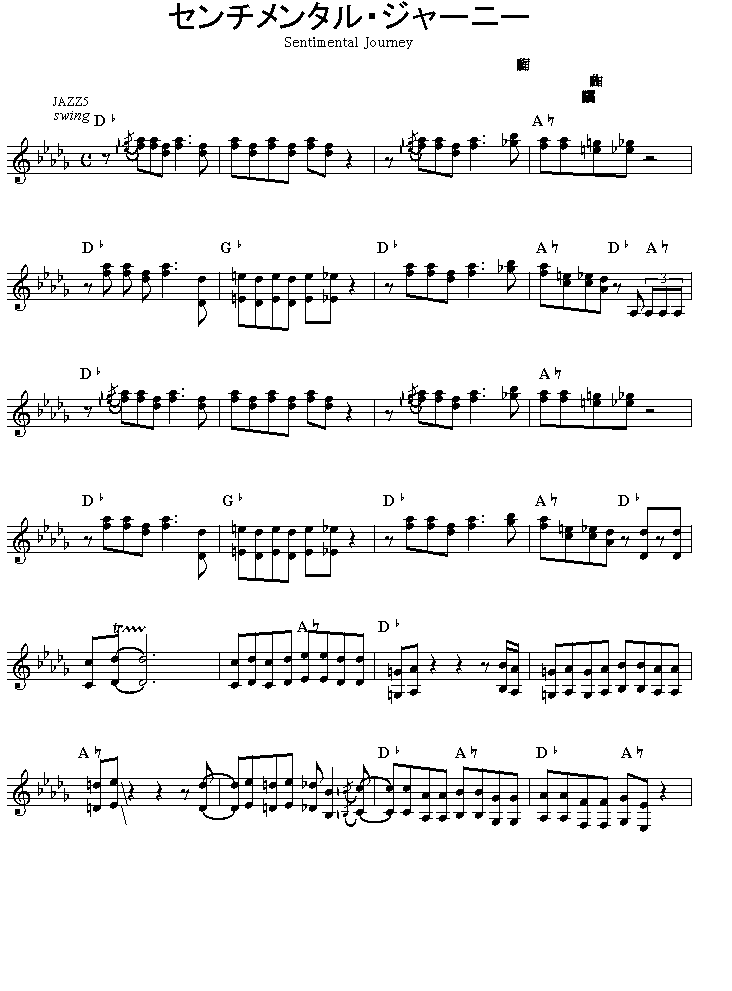
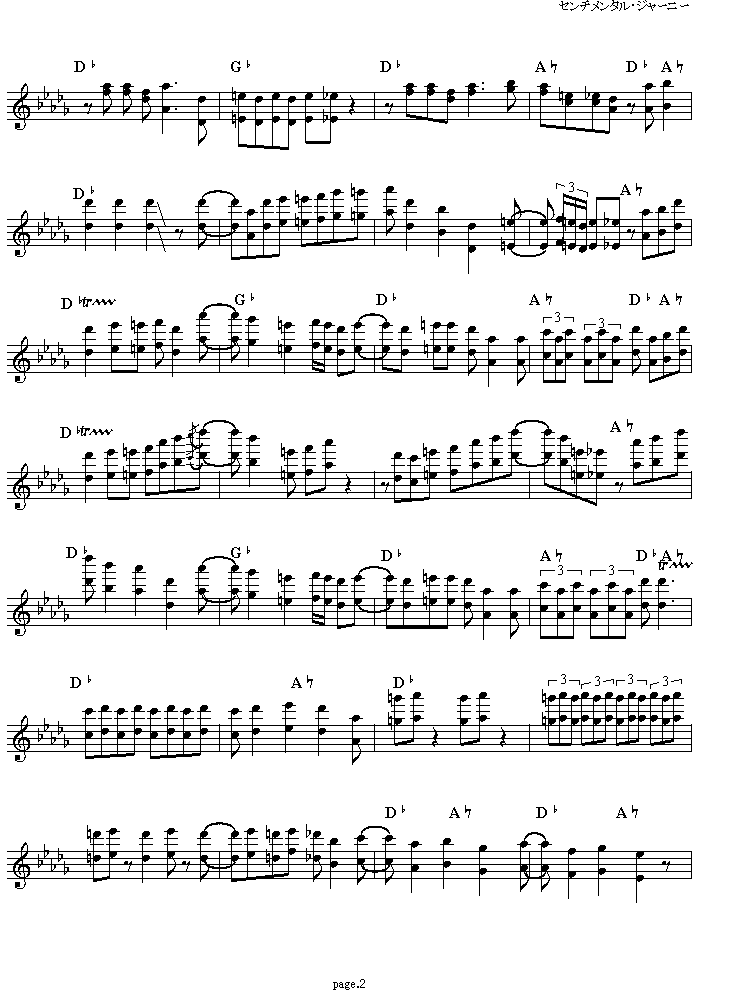
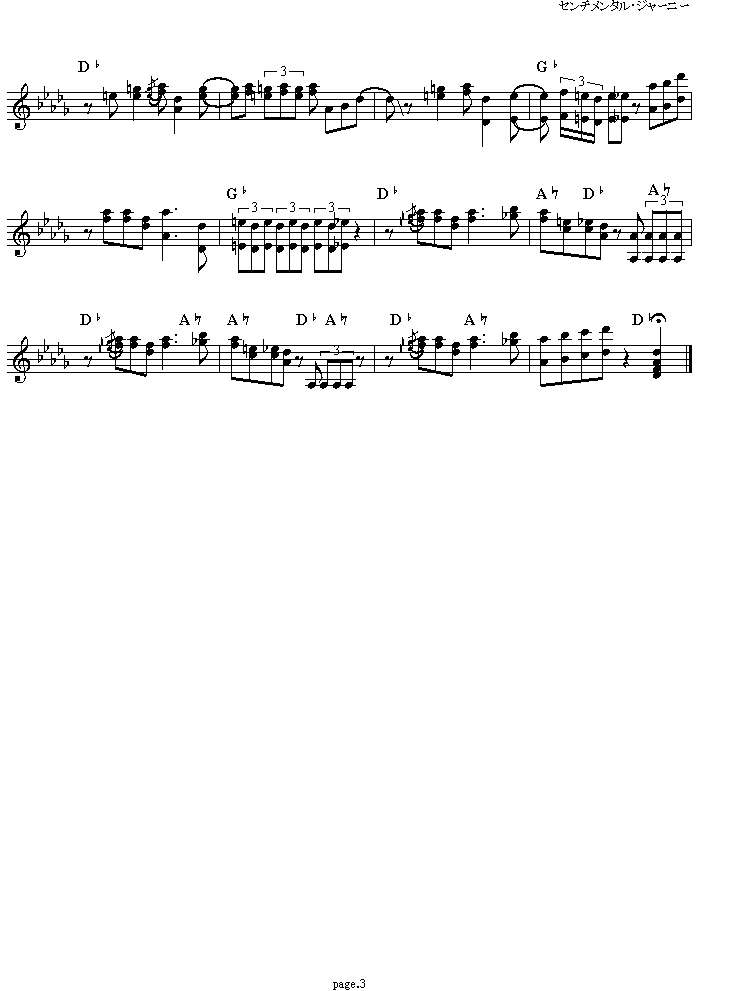
目次へ
|