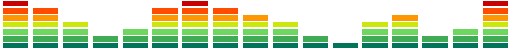
修繕日記のページ

依頼されたり、自前で故障したりして修繕した
ハーモニカの記録を残しておきましょう。
Sorry, Japanese only.
2004年
| 2004年12月23日(木)晴 Super 64, 64X
バルブが数枚そっくり返っているので、一旦はがしたあと、プラスチック部分をしごいてそりを直し、再接着しました。 マウス・ピースとレバーの掃除をしようとしたら、中々ネジが外れません。以前に修理した人がプラスチックのパイプを別のものに替え、しかもボディにしっかり埋め込んであることがわかり、ただただネジを回していけば外れました。しかし、ネジをドライバーで回す作業というのは案外くたびれるものです。とにかく、各部品をきれいにして再度組み立てました。とてもいい感じで鳴ってくれます。 Super 64Xは明日に回そう。「冬のソナタ」が始まってしまいました。 さて、明けて本日はクリスマスです。午前中の練習の後、Super 64Xに取り掛かりました。これもそれほど狂った音は無く、微調整で済みそうです。分解してみると、これまでにも何回も調律されているらしくリードを削った痕がたくさんあります。多少、上見調整が必要なリードもありましたが、すべて調整を終え、宅急便で送り出しました。翌日に着くそうです。 |
| 2004年12月18日(土)晴 古い280
|
| 2004年12月15日(水)晴 全音調律
|
| 2004年11月14日(日)晴 Eバス
オクターブ違いのリードが各穴に入っているが、リードの長さはどちらも同じ。低オクターブのリードは、先に付いている重しの部分が長くなっていて、同じ長さでも低音を出せる仕組みだ。 観察すると、やはり上見が足りない部分が多々見られる。それぞれ、近所のリードと同じくらいに調節していく。低音のものはとても上見が多いがそれだけ必要なのであろう。 このハーモニカは展示品として使われていたとあって、古いためか底面の薄い板がはがれかかっている。ついでに木製ボンドで補修した。 |
| 2004年11月3日(水)晴 Super 64X 2本
翌日改めて全音を吹いてみると、3番のA#が下がっており、変な音もする。リードの端っこが壁に擦れているのだ。調律すると共に、カッターナイフの先で触っているリードを少し削ってやると、正常な音になった。他にも少し下がった音があったが、全音調律の過程で直した。 さて2本目に取り掛かる。こちらも6番のF#がおかしいと書いてある。確かに。強く吹くとこれももっと下がった。折れています。F#ばかり2本折れるとは、何かF#をffで吹く曲を練習しているのだろうか。リードの部品には同じリードが3枚入っているのに、F#だけもう2枚使ってしまった。他の人は他の音が壊れますように。リード交換してそのリードを調律したところ他の音の狂いはないようであり、全音調律の必要性はないと判断した。 以上で修理完了。 |
| 2004年10月31日(日)晴 リード交換
交換は手馴れてきて、スムーズにいった。みわかさんが勉強になるといって、折れ目の入ったリードを持ち帰った。興味を持つのはとてもいいことだ。 |
| 2004年10月13日(水)晴 SCX-64
音が出にくい:観察すると、完全な上見不足があちこちに。調節して、どこでも音詰まりがなくなりました。 低音部のD#が不調:全音調律の過程でOK。 高音部のB#が不調:全音調律の過程でOK。 ときどきレバーが戻らない:明らかにバネが弱い。開き具合を調節したが変わらず。Hohnerのバネに変えてOK。 マウスピース回りには、私の持っているものから比べると改良がなされている。少し進歩しているようです。 カバーを留めるネジは相変わらずよくない。カバーを取り付けるときに、これほどストレスが溜まる機種はないと思う。結局、ネジが片方なくなってしまい(これは当方の不注意だが)、市販のネジをはめてみたらぴったりだったので交換した。それは便利といえるかもしれないが。手抜きのような気もします。また、カバーとリードプレートのかみ合わせもよくない。せっかくリード・プレート側に溝が切ってあるのに、カバーがそれにかみ合わないのです。すぐ滑ってマウスピースの下にもぐりこんでしまいます。すると、レバーを圧迫して動きを阻害するのです。ぜひ、再考願いたい。実際、カバーを取り付けるだけで腹が立ってくる。後日、これに対する対策を講じました。まず、カバーが底面に滑り込みやすいという現象もあるのでよく観察すると、カバーの底面がリード・プレートをはみ出る位に下がっている。で、すぐリード・プレートを外れて底面に回りこんでしまうのです。その原因となるカバー底面を少し上向きにねじ曲げてやったところ、カバーはリード・プレートの範囲内に収まっていてくれるようになった。次に、カバーが上に滑り込んでマウスピースの下にもぐりこんでしまう問題を観察しました。すると、カバーを留めるネジの穴の位置が必要以上にちょっとだけ下にあるようです。カバーをリード・プレートに切ってある溝にあわせると、カバーを留めるボルト、ナットが斜めになってしまい、中々噛み合わなくなるのです。これが大きなストレスの原因になります。そこで、穴の上の方をホンの1mmばかり削って広げてみました。すると、ボルト、ナットが簡単に噛み合ってすぐにカバーを留めることができました。これだ!!!!! ボタンの形状はすこし緩くなった気もしますが、まだ半球状。指の先でボタンを押す人にとっては痛いのです。平らになっているのが誰にでも合う形だと思います。 G#音がカバーを取り付けると変な音になる現象があり、対処に困ったが、再度リード・プレートを外し、よく観察して再組み立てすると、変な音がでなくなった。原因不明ではあるが、なんとなく直ってしまった。 以上の修理、改造でようやく満足な結果が得られました。これでようやく発送できる。 しかし、。。。。。。。。 試し吹きしてみると、最低音部の2穴の音がビビります。観察すると、吹き吸いの切り替えでまだリードが止まらないうちに反対側のリードが動き始めるため、止まらないリードとバルブが触れ合ってビビるようです。バルブをHohner社の低音用の変えてみましたがやはりだめ。低音リードであるがゆえに振幅の幅が大きいのです。Hohner社のリードと長さを比べてみましたが、ほとんど同じです。材質の違いはありそうですが。それでは、と本来必要な上見よりも下げてみました。完璧ではありませんが大分よくなりました。しかし、上見が少ない分、音詰まりもしやすいようです。あまり大きな音を望まず、そっと吹くという配慮が奏者に求められます。 ようやく完成とします。 |
| 2004年10月11日(月)晴 BEBOPチューニング
10 holes奏者でクロマチック・ハーモニカも吹くE.O.さんから、Velvet VoiceとCX-12をBEBOPチューニングしてもらえないかとの依頼があり、持ってきてもらって目の前でチューニングしました。Cの音がダブっているので、その左側のものをBbにするのがBEBOPチューニングで、Brendan
PowerさんのHPで定義されています。http://www.brendan-power.com/ ボタンを押したC#側もBにする必要があるので、都合4箇所です。1音下げるので鑢では追いつかず、電動鑢を使って削りました。 いろいろお話しながらなので、1本の調律だけで3時間もかかってしまいました。そして、後日でよいからと5本も残していきました。なんでこんなに持ってるのか聞いたところ、クロマチックの修理技術がないので駄目になると新品を買い込んだ結果だということです。ちょっとした技術があると、修理修理で2、3本あれば事足りると思われるのですがね。眺めていたので、今後はちょっとした修理は可能でしょう。上見の調整やバルブ貼り替えの効果には驚いていました。 帰られてから、そのうちの1本の調律を終えたところですが、まあ、確かに普通のものとは違います。彼の場合はGのブルースを吹くときにBbをボタンを押さずに出せるのがとても気に入っているようです。Powerさんの説明ではFの曲をボタンを押さずに吹けるという効果もあります。私が気が付いたのは、吹き音のグリッサンドがとてもきれいになることです。ドがダブらないことからそうなるのですね。 ところで、Velvet Voiceを手に取ったのは初めてですが、リード・プレートの厚みのせいか、ずっしり重く、音は出やすいですね。彼はマウスピースを270のものに変えたり、Hard Bopperのものに変えたりしているようです。 さて、後4本調律しなくては。 |
| 2004年10月10日(日)晴 SCX-64 SCX-64は今でも合奏の練習で使っているのですが、マウスピースの下の板が柔らかすぎる金属であるため、ネジを締めすぎたときにへこみができ、それを直してもスライドがすぐへばりつくようになり、掃除の頻度が大変でした。そこで、試しにHohner社の部品と交換してみた。コームの上の金属、スライド、その上の金属の3点をそっくり取り替えて、マウスピースは元のままとしてみました。すると、しっかり互換性があってスライドの動きもスムーズ。よし、これで行こう!また、カバーを留めるネジも駄目になっていて市販のネジでしのいでいましたが、香港のSUZUKIのブースで修理をやっていたのでネジをわけてもらってきたのでそれに交換しました。 これでなんとか購入時の状態のよさに戻った感じ。よかった。 |
| 2004年10月9日(土)晴 SC-56 S.I.さんからSC-56の修理を依頼された。吹いてみると、音がスカスカで隣の音が混じる。マウスピースを分解し、カバーも取り去って観察するがよくわからない。コームに直接空気を吹き込むとしっかりした音が出る。リード・プレートとコームの密着度のせいではない。もう一度、マウスピースだけを組み立てると、今度は前よりずっとよくなった。 これで考えられることは、マウスピースの装着ミスということである。一度外して組み立てるときに、カバーが上の方にせり上がって、しっかりコームと密着していなかったのではなかろうか。 しかし、組み立て直した後でもすこし息が隣に流れる傾向がある。どうも、マウスピースの部品自身に多少密着度が足りない面があるようだ。これは直しようがない。 上見の調節に入った。全体的に上見が少なくて吹きづまりするので、少しずつ調節。低音C#が全く音が出ないが、観察するとゴミがはさまっていたので除去してOK。 調律し始めたが、オクターブ奏法の音がきれいに出ない。マウスピースの隙間のせいなのかオクターブの音以外の音が混じる感じがする。これでは本番でオクターブ奏法を使えそうにない。マウスピースの穴の形が四角であるのも関係しているかもしれない。チューナーを眺めながら全体的な調律を終えた。 仕上がってみれば、中々吹きやすいハーモニカになったと思う。 このハーモニカ、箱が立派で、ボディにもメーカー名がしっかりはめ込まれており、消えることはなさそう。 |
| 2004年9月26日(日)晴 ボタン取れ
昨日の本番直前に、接着剤でくっつけてあったボタンがポロリと取れ、あせりました。最初の1曲はしかたないから直にレバーを指で押しましたが、痛いの何の。学生時代に同様に指から出血したのを思い出しました。休憩時間中にそっとボタンをはめて押してみると、なんとかいけそうなので、後半はなんとか指を痛めずに済みました。 早速修理はしましたが、元々練習に使う予定だったものを本番で使ったのがよくなかった。しかも予備なしで。演奏会は何が起こるかわからないところがあるので、やっぱり予備器は用意しておくべきだったと大反省。 |
| 2004年9月25日(土)晴 レバーの曲がり よく練習するらしくかなり汚れているので、分解掃除の必要性を理解してもらい、ドライバー・セットは100円ショップで買えることを伝えました。 |
| 2004年8月14日(土)晴 香港旅行中に修理依頼が1件あり、これがちょっと古い280だった。
ちょっと古いとは、リード・プレートがプラスチック・ボディに釘止めされ、それが真鍮の釘になっていることを指す。私のそれより古い280はアルミの釘止めだったので、このタイプは見るのが初めてだ。 アルミの釘は、抜くと2度と元に戻らないように曲がってしまって、どうにもならず、ボルト止めに改造してしまったことがある。 真鍮釘は抜いてもまっすぐだったので、普通に折れたリードの交換をした後、組み立てにかかった。しかし手(ペンチ)で押して釘で止めようと思ってもとても密着させることができず、困ってしまった。スースー空気が漏れる。 ふと、リードを外す道具にリベットを入れるだけの穴が開いていることに気が付き、そこに真鍮の釘の先を入れ、反対側から小型金槌で叩いてみた。すると傷付くこともなく、すんなり締まり、リード・プレートがボディに密着しました。これでよし。また一つ、修理技術が身に付いた。 後は最終的な全音調律してOK。 |
| 2004年7月31日(土)晴 自分で木製カバーを付けた方のChromonika IIIではそんな現象は起きないのだが、Romel仕様の280の方では、最高音のE、E#,G,G#、C、C#あたりの音が、少し強く吹くとリードがひっくり返ったように高いピッチになってしまう。リードの取替えが必要かと思って分解してじっくり観察すると、どうもリードを収める空間が浅くなっているようだ。空気の流れがこれで変えられてしまってピッチに影響を与えているのではないかと思われた。
そこで、浅さを少し深く削ってみることにした。 削り始めると、この透明プラスチック・ボディ、なかなか固くて簡単には作業が進まない。でも少しずつ削り出して、リード・プレートを当てて吹いてみると、すこし改良された。どんどん削って、なんとか音がひっくり返らないようになったので、再組み立てしました。強烈な吹き方をしない限りは大丈夫のようだ。 やれやれ、リード取替え作業をしなくてよかった。 カスタム・ハーモニカというと、こんな危険性もある。どうもまだ完成品に至っていないようである。 |
| 2004年7月26日(日)晴 Jens Bungeさんに教わって、William Romelさんに木製カバーのクロマチックを作ってもらった。
具体的には、古い280のリード・プレートを送って、それをプラスチック・ボディにマウントし、マウス・ピース回りをRomel仕様(金メッキ仕上げ)で作ってもらい、さらに木製カバーを付けてもらうというもの。リード・プレートは金メッキされたので、まるで新品のように輝いている。釘止めからネジ止めに変わったので、メンテナンスはしやすくなった。 古い280がベースですから、ストレート配列、ショート・ストロークになっている。 木製ボディだと、風格があり、持っててうれしいという気になる。穴番号は、なし。音色はボディが木からプラスチックに変わったことによる影響が大きいと思われるが、カバーの影響もあると思われる。暖かみのある音になったと思われる。
両者の重さは、金色の方がプラスチック・ボディになってマウスピースが少し大型になったので若干重くなった。 吹いてみて気付いたのは、カバーが木製なのであまり滑らないということ。金属カバーだと緊張したときに結構滑りが出て、掌の汗を拭いたりしていたが、木製カバーではその点、具合がよさそうだ。 |
| 2004年7月20日(火)晴 J.Y.さんからのCX-12ゴールドの修理依頼があり、取り組んだ。外観はきれいなハーモニカだ。私のはブラックで、どうも黒いハーモニカってのは好きになれない。(アッ、音は好きだ。)
7番のBbが狂っているのと12番のC#の音が出にくいというのが依頼内容。7番は別にリードを取り替えるほどではないので鑢で調整。12番は、上げ身が少ないので少し増やしたが、どうも構造上の関係で出にくいような気がしてならない。自分のも出にくいから。前よりは出るようになったが、Cと比べて出が悪い。Cの場合はレバーを押していないが、C#は押すので、その力の入れ具合で角度が変わり、ほんの少しレバーと回りの金属やボディとの間に隙間ができるようである。まあ、普通に吹く分には十分だと思えるが、構造上の改良が必要な気もする。例えば幅を広げてレバーを押す影響がなくなるくらいスライドを長くするとか、回りの隙間をより精密にしてレバーを押しても隙間ができないようにするとか。 さて、依頼の分はすぐ直ったが、全体にオクターブ奏法をしてみると、音が震える部分がたくさんある。それぞれ微妙な鑢がけをしましたが、CX-12のメインテナンス性のよさが実は全音調律していく上で、案外厄介。通常の280や270ではマウスピースを付けたまま調律しているから、削ってオクターブ奏法で確認というのが簡単にできるが、CX-12ではマウスピースが外れている状態なので、削ってマウスピースを付けて、オクターブ奏法で確かめてまた外して削るという操作が延々と続く訳である。 調律し終えましたが、削った後時間が経つとまた狂いが出るということもままあるので、一晩寝かしておくことにした。 でも調律し終わったハーモニカで吹くと、実に気持ちがいい。練習すればするほど音程が狂ってしまうのがハーモニカなので、ぜひ、簡単な調律はできるようになってて欲しい。 |
| 2004年7月12日(月)晴 A調のChordmonica Iの注文がM.S.さんから来ていたので、作成した。C調より音が低いので落ち着いた感じがする。
|
| 2004年7月8日(木)晴 オーストリアのB氏から、一時期Hohner社から発売されていたChordmonica I
のCD付き教則本をいただきました。
Chordmonica I は、クロマチック・ハーモニカのようにボタン付きで、CのハーモニカでいうとC、G7、F、Cdim7の和音が出るようになっているハーモニカです。次のような配列をしています。 吹 C E G C C E G C C E G C 吸 D F G B D F G B D F G B ボタンを押したとき 吹 C F A C C F A C C F A C 吸 C D#F#A C D#F#A C D#F#A メロディを吹きながらベースを入れる演奏をするときに、主要3和音が使えるので、普通のクロマチック・ハーモニカでベースを入れるよりはまともな音が出せます。しかし、半音を駆使した転調などできませんから、クロマチック(半音)・ハーモニカではなく、ダイアトニック(全音)・ハーモニカの部類に入ります。 この程度の配列の違いであれば、C調のクロマチック・ハーモニカのリードを削れば作れそうなので、練習用に使っていたボロボロの270を土台にして作ってみました。 結果良好ですが、C調のハーモニカは音が高いと感じられます。A調、G調などで作れば落ち着いた感じの音になりそうです。今度は、A調で作ってみようと思っています。 |
| 2004年5月4日(火)雨 全連フォーラムで使ったミュゼッとのEの音が下がっているようなので分解して修理した。上下ともかなり下がっている。調律は簡単だったが、バイブレーションの速さを調節しながら観察していると、吹いたときにバイブレーションの振動に合わせてリードが大きく動いたり小さく動いたりしていることに気がついた。2枚のリードの相互作用で実際に音の大きさが揺れてバイブレーションがかかるらしいということが初めてわかった。
|
| 2004年3月10日(水)晴 年休取得。落札した程度の良い古い280が届いていたので修理に取り掛かる。カバーやリード・プレートは新品同様のピカピカ。思うに、未使用のまま保存しておいたもののボディに割れ目が入って使えなくなったのではなかろうか。
分解して驚いた。ボデイに接するマウスピース最下部の板が金属ではなくて赤いプラスチックでできている。こんなモデルを見たのは初めてだ。ボディの割れ目は1箇所だけなので木製ボンドでくっつけて平らな面(今回はPCの上)で固まらせた。リード・プレートを取り付けようとしたところ、割れてはいないがヒビが入っているところがあったので、ボンドを充填しておいた。 全体を組み立てたが、中々よい状態の1本になった。ただし、まだすっかり固まったわけではないので、調律は後回しということにした。 ボディ割れ、一度も吹かずに新古品 |
| 2004年3月7日(日)晴 安く落札した古い280が届いたので修理に取り掛かった。なんと木製ボディが4つに分かれている。分解して、ボディを木工ボンドでくっつけたが、これだけばらばらだとリード・プレートに接する面が平らになるか、マウスピースと接する面が平らになるか自身がもてない。それでまだボンドが固まらないうちにリード・プレートを取り付けて釘止めしておいた。ある程度固まったところで調律に入った。ボディの悪さほどにはリード・プレートは悪くないので、いくつかのリードを削っただけですんだ。A=440の調律になっている。もともと部品用に買ったようなものだったのに
また復活、部品用だったはずなのに |
| 2004年3月2日(日)晴 Hohner Echo Luxeが届いた。湾曲したオクターブ・ハーモニカである。ペイントは剥げ剥げでところどころ鳴らない音がある。分解すると、リードのギャップがまったくなくなっているのが2本。これはすぐに直せるが、思い立ってマイナー・ハーモニカに変えてみることにした。G->A、G->G#、A->G#と変更すればよく、4枚×2で8枚を削った。電動鑢は今日も役に立った。
|
| 2004年2月29日(日)晴 SCHORD20を2台製作。今回は電動鑢を利用してみたが、2音半も音を下げるときなどとても重宝した。ある程度まで削っておいて、その後手で削るとよい。大幅な能率アップである。
工具がウイーンと唸っているので、作業場が町工場のような雰囲気になった。 ちょっとした町工場だね電動やすり |
| 2004年1月10日(土)晴 M.O.さんにSX-64Xを返したが、A2の音がはっきりしないという。また持ち帰って調べたが、どうも上見調整で少し上げすぎたようだ。ほんの少し戻してやると、はっきりした音になった。
|
| 2004年1月5日(月)晴 M.O.さんから5番のD1の音がおかしいとこの前修理したSX-64Xが送られてきた。バルブが取れかかっているのかと思って分解したが、そうではなく、バルブの白い部分とプラスチックの部分がくっついているためという簡単な問題であった。
直して吹いてみると、あちこち吹きづまる部分がある。眺めてみるとかなり上見が少ないことがわかった。前回、調律ばかりしていて上見の調整をしなかったようだ。調整に伴って音程が下がったリードを再調律して一件落着。 |
トップページへもどる
