|
大学ハモソ紹介

関東ハーモニカリーグ2010年5月発行(第54号)に掲載された記事です。
工房クロム 真田正二
東京の4大学、中央、明治、立教、早稲田にハーモニカ・ソサェティ(ハモソ)があります。他に関西に関西大学、九州に鹿児島大学があります。私は早稲田のハモソの出身で、先輩にはライナーズの一員だった波木さん、トンボ楽器会長の真野さん、ノーブランズの鶴田さんと木村さんなどがいらっしゃいます。斎藤寿孝さんは中央ハモソ、寺澤ひろみさんは明治ハモソの出身です。
とはいえ、毎年50人以上のハーモニカ奏者が巣立っているはずですが、そのOB/OG達と、現在のハーモニカ界との接点は非常に少ないように思えます。
ハモソの編成はビッグ・バンドの形態をとっています。40名〜120名と時代、大学によって人数が変わりますが、その構成は大体次のようなものです。
・ソプラノ・シングル・ハーモニカ、アルト・シングル・ハーモニカ、アルト・ホルン・ハーモニカ(各、複数人)
のハーモニカ・パートに加え、次のようなソロ楽器、リズム楽器が入ります。
・フルート、クラリネット・エレキ・ギター、マリンバ、ビブラホン、シンセサイザ、アコーディオン、ピアノ、パーカッション、ドラムス
シングル・ハーモニカというのはクロマチック・ハーモニカの一種です。ボタン式ではなくC調、C#調が同じボディで2段式になっているもので、音は標準配列になっているために複音ハーモニカや10ホールズのようなチグハグ配列の複雑さが無くて済みます。演奏方法がやさしくて合奏には向いています。
レパートリーは、その時代のメンバーが好きな曲を自分たちで選んで編曲するので、映画音楽、ムード・ミュージック、ラテン、タンゴ、ジャズ、ソール、レゲエなどなど、なんでもありです。一時期は専門的すぎて私達卒業生が聴いても知らない曲ばかりでしたが、近年はまた顧客重視の親しめる曲が増えているように思います。
一般的な傾向として、ハーモニカ以外のパートは幼少時代から音楽的素養のある人達ですが、経験が無くも音楽がやりたい人をハーモニカ・パートに勧誘する例が多いようです。
4大学合同コンサートとそれぞれの大学での定期演奏会が二大イベントで、それに向けて年間20〜30曲を練習します。夏の合宿では一気に20曲ぐらい新曲が入りますので、読譜力がぐっと高まります。レパートリーの譜面は特にやさしく吹けるような調を選ぶわけではないので、入部してすぐb4個の調や#3個の調を吹き始めたりします。
ハーモニカ・パートのうち、志のある人がボタン式クロマチック・ハーモニカに挑み、バンドをバックにハーモニカ・ソロをこなします。私達の時代ですと、そういう人は学年に一人程度というエリート・コースでしたが、近年は大抵の人がやるように一般化されてきました。
近年のもう一つの変化としては、4年生が就職活動のために6月ごろの4大学演奏会に全然参加していません。暮れの定期演奏会では参加するようです。4年時の定期演奏会というのは送られる主役ですので自分のときは感動で一杯でした。
さて、卒業して就職してしまうと、ハーモニカはホンの趣味として細々と吹いて行くことになっていると思います。全日本ハーモニカ連盟や関東ハーモニカ連盟があることなど全く気付かずに会社で仕事に頑張っていることでしょう。私はたまたま41歳ぐらいの時に鶴田先輩に紹介された「ピクニック・コンサート」に参加して初めて、こんなに盛んなハーモニカ界というものがあることに気付いて、本格的にハーモニカに戻りました。いくつかのバンドに属し、指導もやってみて、今はどっぷりとハーモニカ界に使っております。
もしハモソのOB/OG達がもっとハーモニカ界に戻ってくれば、今のハーモニカ界ももっともっと発展するのではないかなと思います。なにしろ、若い時に培った読譜力、リズム感は、定年近くになって初めてハーモニカに接する人達よりはずっとすぐれています。重要なパートを担当したり、指導者として活躍する場があるのではないかと思います。エールを送ります。「来たれ、ハモソOB/OG!」
|
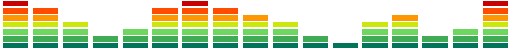
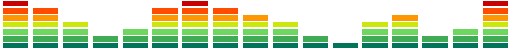
![]()