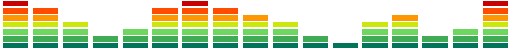
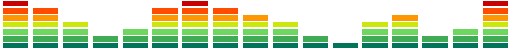
|
クロマチック・ハーモニカ入門 関東ハーモニカリーグ2009年10月発行(第50号)に掲載された記事です。 工房クロム 真田正二 クロマチック・ハーモニカをこれから始めたいという方のために、これまでポピュラー音楽用の指導をしてきた経験から、これだけやればなんとかなるというポイントをまとめてみたいと思います。 パッカー奏法とタング・ブロック奏法 咥え方 腹式呼吸 低音部の発音 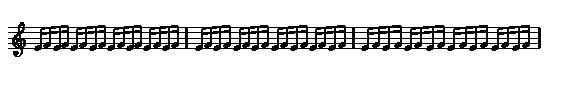
空気の流れが口の中で変に方向を変えられたりせずに、素直にハーモニカに流れなければなりません。頬に空気を逃がしたり、吹きと吸いで口の形が変わっていると空気の流れが乱されるのです。たとえばオクターブ奏法で次を試してみてください。 高音部の発音 また、風圧の関係で音が出にくいと感じて、一生懸命強く吹き吸いする人がいますが、そうすると、高音部の音が割れます。クロード・ガーデンさんに高音部がきれいな音になる秘訣を聞いた時、ニヤリと笑って、「シーッ、弱く吹くんだよ。」と教えてくれました。弱めに吹いてもちゃんと周りに聞こえる音量は出ているのです。力を抜いて、音が出ていたらそれ以上強く吹き吸いしないようにしてみましょう。きれいな高音が手に入ります。 音階練習 ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド と吹く場合に穴は4つしか使いません穴の移動は3回しかないわけです。初めてクロマチック・ハーモニカを手にしたとき、これにはカルチャー・ショックを受けました。そして取り組んだのが音階練習でした。 リピート記号の間を、足で1拍ずつの拍子をとりながら、リピート記号の間を何回でも繰り返します。足のうごきはリズム感を養う上でも重要です。最初は吹きながら穴の移動を意識していないとうまく吹けませんが、繰り返し練習するうちに、それが無意識でできるようになります。それこそがこの練習の狙いです。
出だしの音が吹き音の「ド」から吸い音の「レ」に変わるので、また新鮮な気持ちで取り組めます。そして同様のことを「ミ」から始める、「ファ」から始めると変化させて「シ」から始めるところまでいければ、ハ長調の音階を全制覇したことになります。 速吹き練習
音階練習と同じようにリピート記号の間を、足で1拍ずつの拍子をとりながら、リピート記号の間を何回でも繰り返します。今度は16分音符ですので、足1泊分で音が4つ出ることに注目してください。最初はゆっくり、段々早くできるようにしていきますが、一拍で音が4つ出ることをきちんと守ります。 できるようになったら、出だしの音を「レ」から、「ミ」から、・・・、「シ」まで変化させて練習します。さあ。ハ長調の速吹きを全制覇しましょう。この・・・の部分をちゃんとやるかどうかで実力に差が付いていきますので、心してかかってください。 速吹きをしっかりやると、吹きと吸いで横隔膜の上下運動の切り替えが素早くできるようになりますので、実はスローの曲の滑らかな演奏にもこの訓練が役に立つのです。 音色作り プロの奏者の演奏を聴くと、例外なくきれいなビブラートが付いた音を出しています。そこで、クロマチックの演奏を目指す人は、早い段階からビブラートをかけられるように取り組まなくてはなりません。 ビブラートは音の揺らぎです。ハーモニカの音を揺らすにはいろんな方法があります。 ・ハンド・カバー奏法 それぞれのビブラートには特徴があり、奏者によって音色が異なります。それぞれの方法について、私のウェブ・サイト「工房クロム」(これで検索できます)から辿れる「インターネット教室」で説明してありますので、興味のある方はぜひ訪問してください。 グループで合奏を楽しむことも多いと思いますが、その場合、個性が強すぎる音作りをすると、他のメンバーとうまくハモらないということが起きます。その場合は、たとえ個性が強い音色を持ったとしてもそれは殺して、素直な音作りで演奏します。その時に使うビブラートは、「ハンド・ビブラート」が万人向けでよいと思います。 一流奏者の音色から学ぶ 「東京クロマチックハーモニカソサェティ」は一旦解散宣言されましたが、実はインターネット時代に会費を集めて会誌を発行するのは時代にそぐわないというのが一つの理由でした。そこで、ブログ(Blog)という手段で情報を発信し続けようということになりました。ブログでの重要な記事として、世界の奏者の動画へのリンクをしております。「東京クロマチック」で検索できますので、ぜひ訪れて一流奏者の演奏をお楽しみください。 |
トップページへもどる |
お話へもどる |
![]()
©copy right 2009 Shoji Sanada, All rights reserved