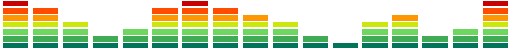| ハンディ・コード・ハーモニカ S-Chord 口琴藝術No.167(2004年夏)に掲載された記事です。 1.はじめに
図1瀬戸の花嫁のコード譜 2. VinetaHohner社が販売しているハンディなコード・ハーモニカにVinetaがあります(図2)。長さは複音ハーモニカをちょっと長くした程度ですから十分鞄に納まります。
図3 Vinetaのメジャー・コード
図4 Vineta のマイナー・コード ありがたいことに、「瀬戸の花嫁」で使うコードがこの2本の組み合わせで十分足りているのです。 それでは、Vinetaがあればそれでよいのでしょうか。そうとは言い切れません。C調のハーモニカの一番吹きやすい中音域のドは5線譜でいうと第3間にあり、そこから始まる音域はほとんど5線譜をはみ出すくらい高い音域なのです。したがってC調の曲はおおむねキンキンした高い音程の演奏になってしまいます。そこで、複音ハーモニカ教室でもC調とC#調のハーモニカを使いながら、調子記号として#が1個付いたG調とかbが1個付いたF調の曲を吹くことがよくあるのです。(それ以上#やbを増やすと複音ハーモニカではとても演奏が大変になるので、ほとんど使われません。) コード・ハーモニカでは一般的に#が1個増えれば位置が右隣に移り、bが1個増えれば同じく左隣に移るという関係がありますから、#1個の場合、C/G/DとAm/Em/Bmという組み合わせ、b1個のときであればBb/F/CとGm/Dm/Amという組み合わせであれば同様に伴奏が可能なのですが、残念ながらそのような製品は市販されていません。そういう意味で、Vinetaは複音ハーモニカ教室で汎用的に使えるハンディ・コード・ハーモニカとしては不十分なのです。 3. SCH-24 鈴木楽器からはSCH-48のコード数を半分にしたSCH-24という小さ目の2段式コード・ハーモニカが販売されています。SCH-24のコード配置は図6のようになります。
図5 SCH-24
注:+はaug、−はdimを表す 図6 SCH-24のコード配置 このコード・ハーモニカでは残念ながら前述の「瀬戸の花嫁」の伴奏ができません。よく使われるコードは何かという視点で設計されたのではなく、上下段の配置がSCH-48と互換性が取れるように設計したため、Emが存在しないからです。当然#が1個のG調の曲やEm調の曲の伴奏はできません。#1個で右隣に移りますから、必要なコードが右端からはみ出たところにあるからなのです。作りがよく、大きさも手ごろなのに残念至極です。なお、bが1個のF調やDm調の曲は左隣に移りますので、十分伴奏できます。4. CHORDET20 中国のVictory社からCHORDET20という2段式のコード・ハーモニカが販売されています。日本で取り扱っている代理店は無いようですが、このご時世ですからインターネット経由で購入することができます。同じ名称でHuang社製のものもありますが、コードの配列が下段の吸う音で若干違いがあります。どちらも大きさはVinetaの長さとあまり変わらず、鞄に納めるにはよい大きさです。 CHORDET20のコード配置は図8のとおりです。残念ながらこのコード・ハーモニカでも「瀬戸の花嫁」の伴奏はできません。E7が存在しないからです。E7はAm調の曲では必須ですから、日本の曲では致命的です。
図8 CHORDET20のコード配置 5. S-Chord20 このように見てきますと、いずれのハンディ・コード・ハーモニカも複音ハーモニカ教室で使うには不十分といえます。 しかし、これらの構造や大きさは使いやすいハンディ・コード・ハーモニカを考案するのによいヒントを与えてくれました。Vinetaのコード配置とSCH-24やCHORDET20の2段構造が鍵です。 そこで、筆者はCHORDET20を改良して図9のコード配置を持つハーモニカを作成しました。名前がないと困るのでS-Chord20と名付けました。
図9 S-Chord20のコード配置 作成するといっても、ハーモニカのリードはヤスリで削ることによってかなり音程を上げ下げすることができますから、時間さえかければ作ることができるのです。できあがったS-Chord20の外観は、図7と同じです。 さて、S-Chord20はCHORDET20と同様5列のコードが接続された2段のハーモニカに配置され、吹き吸いで異なるコードが出せますから合計20のコードが出せます。中央の3列に注目すると、実はこれはVineta2本の組み合わせとまったく同じです。したがって「瀬戸の花嫁」の伴奏に使うことができます。それに左右に1列ずつのコードを配置しましたが、左はb1個の調子用、右は#が1個の調子用に自然に拡張したコードになっています。つまり、「瀬戸の花嫁」をC調からF調に転調したときは左3列、またC調からG調に転調したときは右3列を使って伴奏することができるのです。問題点としてはD7とA7がそれぞれ2箇所にありダブっていることですが、転調でコード配置が平行移動できる利点を考えると、無理にaugやdimをここに埋め込むより自然な方法であると考えています。 6. S-Chord10 さて、S-Chord20にはaugやdimのコードが一つもありません。無くてもよいのでしょうか。これらのコードは時にはとても重要なものです。たとえば、「浜辺の歌」ではソ ソ − レ ソ − レ# ソ − − ミ − という場所でG、G#+、Aというようなコード進行がなされ、このG#+というコードが大変重要な働きをもちます。 そこで、augやdimのコードを吹けるようにする方策を考えました。 Victory社は別にCHRODET10と呼ぶCHORDET20をさらに簡単化した1段式のコード・ハーモニカを販売しています。CHORDET10のコード配置は図11のとおりです。
図11 CHORDET10のコード配置 このコード・ハーモニカは7thコードを犠牲にしてメジャーとマイナーのコードを埋め込んである簡易型のコードなのですが、7thを欠いているので教室で使うには物足りません。
図12 CHORDET10のコード配置 コードの展開形の同値関係により、augコードには、C+ = E+ = Ab+ C#+ = F+ = A+ D+ = F#+ = Bb+ Eb+ = G+ = B+ dimコードには C- = Eb- = F#- = A- C#- = E- = G- = Bb- D- = F- = Ab- = B- という関係が成り立ちますから、S-Chord10ではすべてのaugとdimのコードを出すことができるのです。コード名の並び方はaugはメジャー系の並び、dimはマイナー系の並びと同じにしてありますので、覚えるのも簡単です。また、改造の容易さから言ってもaugはメジャー・コードから、dimはマイナー・コードから削り出しやすいのです。 さて、作っても持てないようでは伴奏に使えません。持ち方については、全部で3段のハーモニカを持つことになりますが、C-Chord20が蝶番に繋がれた2段式ハーモニカなので、さらにS-Chord10を手に構えて持つことは十分可能です。S-Chord10の方は蝶番に繋がれていないので、掌の操作により、自由に操作できることも実演で体験しました。 augやdimの出てこない曲もたくさんありますので、通常はS-Chord10を使わないでおいて、必要に応じて追加して持てばよいと考えています。 なお、S-Chord20とS-Chord10については、改造依頼、供給依頼があるようでしたら、ぜひお受けしたいと考えております。 |