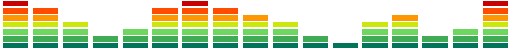
|
コード・ハーモニカ入門 未発表 目次 いろいろなコード・ハーモニカ コード・ハーモニカの仕組み 主要3和音 循環コード コード名の覚え方 色々なリズム ワルツ 後打ち ビギン 4つ打ち 8つ打ち ダブル・タンギング 遊び心 お手本 コード・ハーモニカによる遊び コード・メロディ アンサンブル用のハーモニカに、和音でリズムを担当するコード・ハーモニカがあります。メーカにより色々な製品が出ています。 Hohner社製Accorda-267/384 2段のハーモニカにコード音が埋め込まれ、Major、Minor、7th、Aug、Dimの5コード・パターンが12調子全部について出せます。MajorとMinorは吹音、それ以外は吸音です。木製ボディで上品な音色、コード・ハーモニカとしては、最高級品といってよいでしょう。バルブもクロマチック・ハーモニカと同じものが使われており、へばりつきにくいです。 HOHNER社製Vineta-ORCH4/48 1本のハーモニカに6つのコード・パターンとバス音を備えており、メジャー用3種類、マイナー用3種類が販売されています。MajorとMinorは吹音、7thは吸音です。このうち、F/C/GとDm/Am/Emの2本を、複音ハーモニカを2本持つのと同じ持ち方をすると、教室レベルで必要なコード・パターンがほとんど出せますので、中々重宝します。 Suzuki社製コードハーモニカ-SCH-48 上記Accorda-267/384と同じコンセプトに基づいたコード・ハーモニカ。プラスチック・ボディであるため、機密性は高いが音質は軽くなります。この機種用のマイクロフォンが販売されており、有利な面があります。バルブがへばりつき易いという指摘がよくあります。 Suzuki社製コードハーモニカ-MAJ-12/MIN-12 SCH-48の半分のコードを持つお手軽版コード・ハーモニカ。また、各コードの左にバス音も配置してあり、トリオではなくデュエットで使えることも狙っています。プラスチック・ボディで、バルブをなしにしたところに工夫が見られますが、筆者はMIN-12のコードの選び方に異論をもっており、あまり使い勝手がよいと思っていません。 Huang社製#121 CHORDET 20 2段のハーモニカにMajor、Minor、7th、Dim7のコード20個とバス音が付いています。ただ、Dim7を入れたため、日本で必要となるE7の和音がないという不便さがあります。 Tombo社製No. 1151 メジャー・マイナー・コード、No. 1152 セブンス・コード どちらもは吹音のみで、No.1151は1本の2段式ハーモニカの上下にMajorとMinorが12個ずつ埋め込まれています。No.1152は1段式ハーモニカに7thが12個埋め込まれています。この両方を複音ハーモニカのように持って演奏します。 Tombo社製コードハーモニカ−8-no.1153 吹音のみで、1本の2段式ハーモニカの上下にそれぞれBb、F、C、G、D、A、E、BとBbm、Fm、Cm、Gm、Dm、Am、Em、Bmが埋め込まれています。7thがないので、Majorで代用にします。安くて手軽に使えます。 手作りAhdaChorda 10 holesハーモニカは吹くとMajor、吸うと7thコードが出せることを利用して木枠の中に上下6本の10 holesハーモニカをはめ込んだ自作のコード・ハーモニカ。Hohner社のVinetaと同じ使い方が可能ですが、ハーモニカの種類を入れ替えられるので、任意の調子に合わせることができます。通常の教室レベルの伴奏にはもってこいですし、時にはメロディを演奏することもできます。 筆者はAccorda-267/384、CHORDET 20、コードハーモニカ−8、AhdaChordaを保有していますが、今後の話はAccorda-267/384を基に展開していきます。 コード・ハーモニカを一度も吹いたことのない人にとっては、この長いハーモニカは脅威の的かもしれませんね。一体、どんな仕組みになっているのだろうと不思議に思っていることでしょう。また、仕組みがわからないと中々吹いて見ようという気も起きないことでしょう。 まず、コード・ハーモニカは、和音を出すハーモニカだということを理解しましょう。コード(Chord)というのは、和音のことです。コード・ハーモニカでは1ブロック8個の穴を同時に咥えます。わかり易い和音で説明しますと、C調の主和音であるCの和音の場所を吹くと、次の音が同時に鳴ります。上段は1オクターブ低い音になっており、全体として音域の広い厚みのある和音が得られます。 Cの和音(下線付きは1オクターブ低いことを示す、以下同様。)
また、最初は戸惑うかも知れませんが、同じブロックを吸うと、C調の属七和音である次のG7の和音が出ます。 G7の和音
コード・ハーモニカは2本の組みでできており、上段のハーモニカは長調および属七の和音、下段のハーモニカは短調の和音および増3度、減3度の和音が配置されています。わかり易い短調の和音でいいますとAmの和音は下のようになっています。 Amの和音
増3度の和音というのはC調でいいますと、C+とかCaugとか書かれる和音ですが、次のような和音となっています。 Caugの和音
また減3度の和音をC調でいいますとC-とかCdim(厳密にはCdim7)とか書かれる和音ですが、次のような和音となります。 Cdim7の和音
なんだか難しい話になってきていますが、コード・ハーモニカのよい点、楽な点は、このような和音があらかじめ1ブロックの中に用意されていますので、ピアノやギターのように和音の構成音によって指の形を変える必要がないということです。ただその場所を選んで、吹き吸いするだけでいいのです。 音階についておさらいしますと、音階は次の12の音からできています。 ド レb レ ミb ミ ファ ファ# ソ ラb ラ シb シ アルファベットで書くと次のようになります。 C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B また、これらの各音を基点とした12の調子があります。したがって、長調、短調、属七の和音は、この12調子分揃っています。 コード・ハーモニカには、これらの和音が次のように埋め込まれています。 上段(長調、属七の和音、薄い色は吹いたとき、濃い色は吸ったときの和音、以下同様。)
下段(短調、増3度、減3度)
よく見ると、増3度や減3度の和音は12調子分揃っていませんね。どうしたのでしょう。足りないのでしょうか。実は、ちゃんと足りているのです。アルファベットの音名で説明しますと増3度のC+の和音は12の音のうち、次の太字の音からなっています。 C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B これは12の半音階を4つの半音階ごとにくぎったものになっています。これらの構成音の増3度の和音を作ってみますと次のようになります。 E F F# G Ab A Bb B C Db D Eb Ab A Bb B C Db D Eb E F F# G つまり、E+もAb+も同じ構成音から成り立っていることがわかります。すなわち、これらは同じ和音の展開形になっているのです。したがって、増3度の和音は12調子全部を揃える必要がなく、 C+ = E+ = Ab+ Db+ = F+ = A+ D+ = F#+ = Bb+ Eb+ = G+ = B+ の4種類があれば十分だということになります。 同様に減3度の和音C-について考えてみますと、減3度のC-の和音は12の音のうち、次の太字の音からなっています。 C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B これは12の半音階を3つの半音階ごとにくぎったものになっています。これらの構成音の減3度の和音を作ってみますと次のようになります。 Eb E F F# G Ab A Bb B C Db D F# G Ab A Bb B C Db D Eb E F つまり、Eb-もF#-もA-も同じ構成音から成り立っていることがわかります。したがって、減3度の和音は12調子全部を揃える必要がなく、 C- = Eb- = F# = A- Db- = E- = G- = Bb- D- = F- = Ab- = B- の3種類があれば十分だということになります。 厳密には7つの位置で増3度と減3度の和音をすべて出すことができますが、コード・ハーモニカにはいくつかをダブらせて埋めこんでありますので、必要に応じてそれらを替え手として利用することができます。 さて、コード・ハーモニカの構造はわかりましたが、各和音の並べ方を見て下さい。 Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B なんだか複雑ですね。覚えにくいったらありゃしない。どうしてこんな順番に並んでいるのでしょう。なにか理由があるのでしょうか。 じつはこれが大ありなんですね。各調子の#やbの付け方をおさらいして見ましょう。C調は#もbも付いていない調子です。#が1個の調子はG調になります。#が2個はD調、#が3個はA調、…。おや、和音の並び方と関係がありそうですね。そうです。コード・ハーモニカの和音の並び方は、C調を中心として#が増えるにつれ右に行くように並んでいるのです。それではbとの関係は? bが1個の調子はF調、2個はBb調、3個はEb調、…。やはりC調を中心にbが増えるにつれ左に行くように並んでいます。すなわち一つ隣は、右向きには完全5度上、左向きには完全4度下の音になるように配置されているのです。 この並べ方のメリットについては、各調子の主要3和音を考えてみるとよくわかります。基本的なC調で考えて見ましょう。C調の主要3和音は、主和音がC、下属和音がF、属7和音がG7です。コード・ハーモニカで見ると次の太字の部分がC調の主要3和音です。
つまり、穴の位置でいえば、隣り合ったわずか2つの位置で主要3和音が出せてしまうのです。属7の和音をわざと左にずらして埋めこんである理由もここにあります。すなわち、ずらさなければ3ヶ所の動きとなるところをずらしてあることによって2ヶ所の動きで済むように、より動きを少なくて済むように配置してあるのです。実際、欧米の民謡などには、CとG7の2つの和音しか使わない曲(例:ヒンキ・ディンキ・パーリ・ブー、ジャンバラヤなど)もあり、その場合には、1ヶ所の穴の吹き吸いで伴奏ができてしまいます。 #が1個ついたG調の主要3和音を見てみましょう。G、C、D7です。コード・ハーモニカ上では次のとおりです。
つまり、#が1個つけば、右へ1ポジションだけ移動すればよいのです。そっくり並行移動するだけですから、慣れるとC調の楽譜を見ながらD調やA調で伴奏することも簡単にできます。なんだか、フレットを変えるだけのギターの伴奏とよく似ていますね。 bの場合も同様です。b1個のF調は、左へ1個ずらせばよいのです。
#が6個のF#調(あるいはbが6個のGb調でも同じ)ではちょっと面倒ですね。
上のようになって、端っこと端っこを吹くハメになります。大変ですが、これがまた面白いのです。コード・ハーモニカを大きく動かすオーバーなアクションは、観客に大受けすることが確実で、昔からハーモニカのコミック・バンドでよく使われています。 この辺で例題を出してみましょう。次に掲げるのはC調とD調の「草競馬」の伴奏です。CとD、右へ2ポジション移るだけで動き方が全く同じだということを実感してみてください。 C調「草競馬」 |
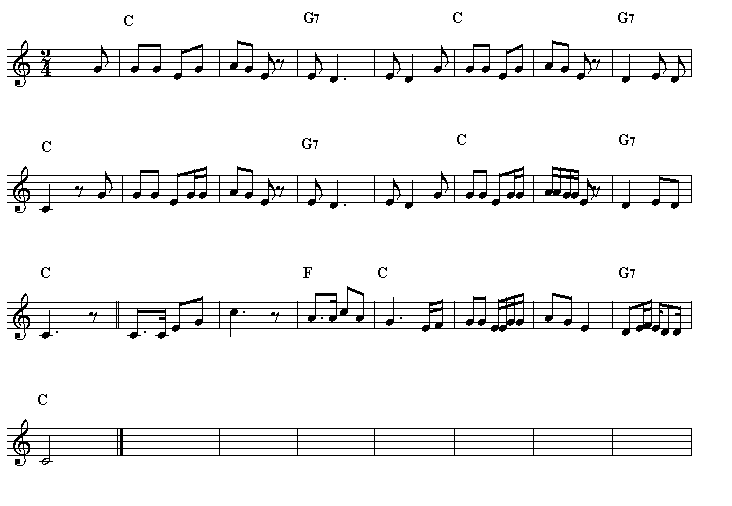
| D調「草競馬」 |
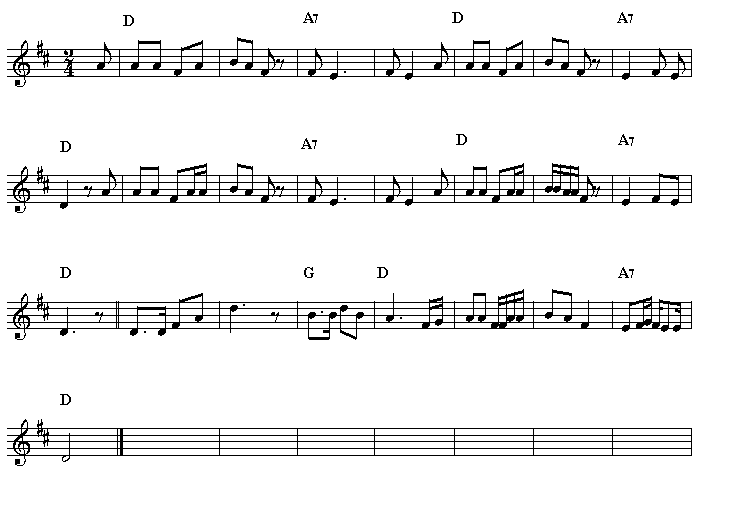
次に、短調の主要3和音について考えて見ましょう。#もbも付いていないAm調の主和音はAm、下属和音はDm、属7和音はE7です。コード・ハーモニカで見ると次のようになります。
今度は下段と上段の両方のハーモニカを使わなければなりませんが、やはり動きとしては2ヶ所で済みます。bが1個付いたDm調は次のように左へ1ポジション移動します。
短調の場合は、#が3個付いたF#m(Gbm)で端から端への移動パターンが出てきます。
練習曲には、「月の砂漠」を挙げておきましょう。AmとDm、左へ1ポジション移動するだけですね。 Am調「月の砂漠」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
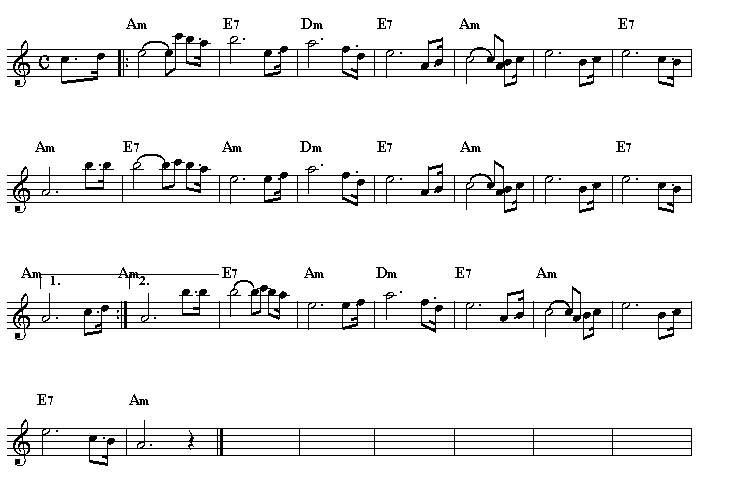
| Dm調「月の砂漠」 |
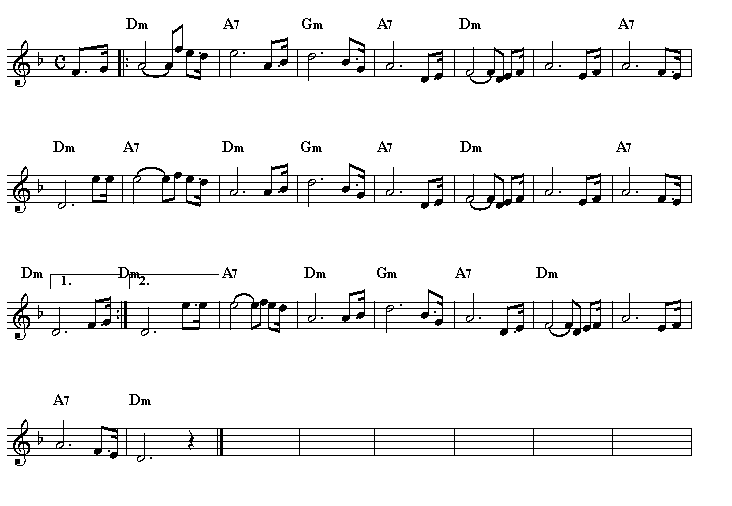
|
さて、音楽は主要3和音だけからできているわけではありません。主要以外の和音がたくさん使われます。日本のフォーク・ソングや歌謡曲では、長調と短調が混じった、循環コードという和音がよく使われます。循環コードでは、C調でいうと次の和音がよく使われます。 C、Am、Dm、G7 これらがコード・ハーモニカではどこに出てくるか調べてみましょう。
CからAmへ飛びますが、このパターンはよく現れますので、よく練習して確実に飛べるようにしておきたいものです。ハーモニカ・トリオでよく演奏される曲に「パーフィディア」というラテンの曲がありますが、この曲の出だしのコード・パターンは次のようなものです。 |C Am |Dm G7 |C Am |Dm G7 |C Am |Dm G7 |E7 | | |C Am |Dm G7 |C Am |Dm G7 |C Am |Dm G7 |E7 | | まさに循環コードのお手本のような曲です。この曲を練習しておけば、フォークソングや歌謡曲にも応用が効いて便利です。 実際の演奏では、主要3和音や循環コードだけでなく、いろいろな和音が出てきますから、コード・ハーモニカ上のコードの配置をしっかり覚えておく必要があります。 Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B この配置は、右半分を覚えれば左半分はそれらにbが付いているだけですから、右半分をしっかり覚えましょう。 エフ シー ジー ディー エー イー ビー 英語で読むと上の用になりますが、少し読みにくいので、私は語呂のよいドイツ語読みで覚えています。(卒業して頭に残っているのはこれ位のもので、悲しいものがありますが。) エフ ツェー ゲー デー アー エー ベー また、一つおきに1音違いの音があるということを知識として知っておくと、実際の演奏のときに役立つことが多いものです。 Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B コード・ハーモニカは伴奏を担当する楽器ですので、ギターのコード打ちの役目や、ドラムのビートを刻む役目を担っています。とくに他にリズム楽器がいない小編成のバンドでは、唯一のリズム楽器としての活躍が期待されます。ラテン系のリズム、ジャズ系のリズム、フォークソング、ニューミュージック、ロック、バラードなどなど、いろんなリズム・パターンをマスターしましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワルツ
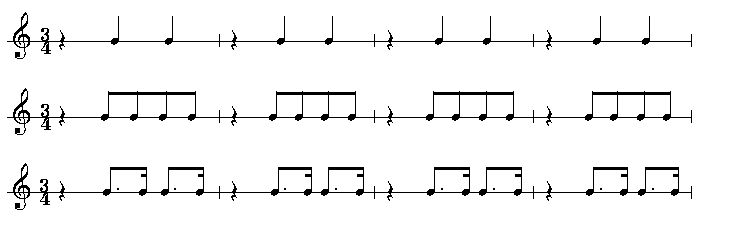
後打ち
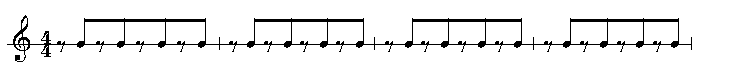
タンゴ
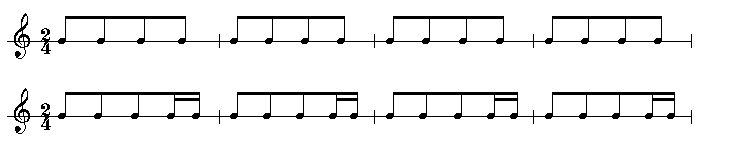
ハバネラ
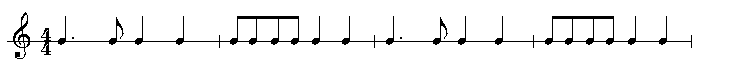
ビギン
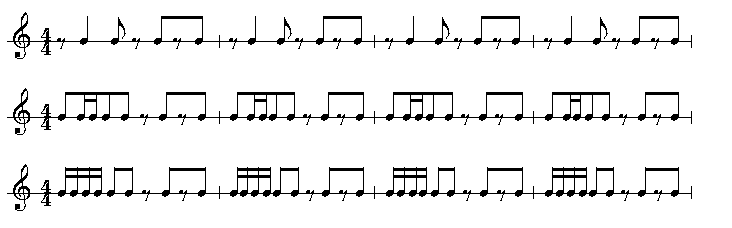
チャチャ
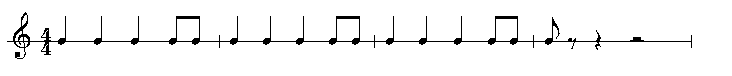
マンボ
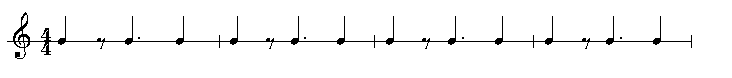
ルンバ
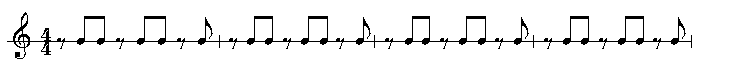
ボサノバ
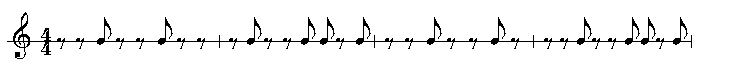
スイング
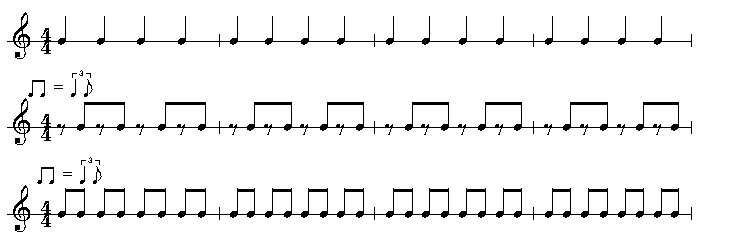
スロー・ロック
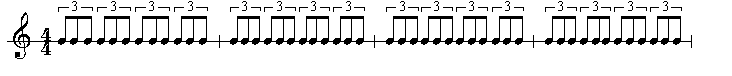
フォーク
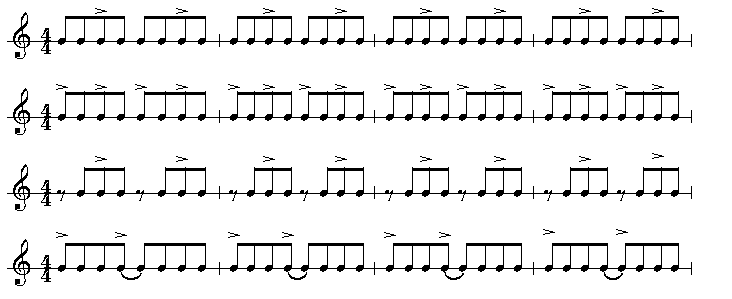
|
上図に基本的なリズム・パターンを示しましたが筆者のこれまでの経験から気の付いたことをいくつか述べておきましょう。 3/4のワルツの基本はン チャッ チャッ ン チャッ チャッという感じでしょうが、1995年の横浜大会のワークショップでアドラー・トリオのドゥロー・アドラーさんが講習した説明では、最初のンの所では休まないでズーとおとを出した方が厚みのある伴奏になるとのことでした。つまり、ズー チャッ チャッ ズー チャッ チャッという感じにするわけです。特に、合奏でバス奏者が休んでいるときなんかにこの奏法をしますと、リズムが乱れることなく練習をすることができます。 ウィンナ・ワルツのテンポの取り方って、普通のワルツとは違った独特のものですね。私自身はまだウィンナ・ワルツの伴奏をしたことがないのですが、もしやるとしたら、この独特の間の取り方をよく研究しないと、まずウィンナ・ワルツっぽくならないだろうなと感じています。 行進曲やポルカなどで後打ちのリズムを取ることがよくあります。ン チャ ン チャ ン チャ ン チャ。これはかなりの熟練を要するリズムです。ピアノであれば一人で左手のバス、右手のコードを弾きますのでずれることはないと思うのですが、バスとコードを別々の人が担当する場合には、両者がだんだんずれてきて悪い時には同時打ちになったりします。特に速いテンポの曲ではこの傾向が強くなります。私も初期の頃はこれに随分悩まされ、満員の通勤電車の中で頭の中でン チャ ン チャをイメージする訓練をよくしたものでした。 前記のアドラ−さんは、やはりンの所をズと軽く音を出し、ズ チャ ズ チャ ズ チャ ズ チャという感じで音に厚みを出しているとのことでした。 ビギンのリズムは、ン チャー チャ ン チャ ン チャ ン チャー チャ ン チャ ン チャとなりますが、ここで注意しなければならないのはチャーの部分をしっかり延ばすことです。これを理解しないでいると、お客さんにはン チャ ン チャ ン チャ ン チャ ン チャ ン チャ ン チャ ン チャと聞こえてしまいます。これでは単なる後打ちと同じなので、とてもラテンのリズムには聞こえないのです。 チャーをしっかり延ばしても、そもそも後打ち的なリズムなのですから、後打ちの項で述べたのと同様にズレが生じやすいリズム・パターンだと言えます。ズレを出さない手段としてよく使われるのが、最初ンのような休みのところで音を出すことです。プロの演奏を聞いていても、ジャ チャー チャ ン チャ ン チャ ジャ チャー チャ ン チャ ン チャとかジャカジャカジャジャン ン チャ ン チャ ジャカジャカジャジャン ン チャ ン チャのパターンがよく現れ、また音の厚みも増します。 スウィングやタンゴでは1小節の中に4つ打つパターンがよく出てきます。しかし、スウィングとタンゴではその打ち方がまるで違います。ギターでも両者のリズム打ちははっきり違う刻み方をしますが、コード・ハーモニカでもそのニュアンスの出し方を変えなければなりません。 スイングではチャッ チャッ チャッ チャッ と軽いタッチでありながら、ギターで打った後左手を緩めるのと同様に、呼吸を軽く止めてやります。 タンゴでは、チャッ チャッ チャッ チャッと強いアクセントの付いた4つ打ちであったり、チャッ チャッ チャッ チャッと2拍ごとにアクセントをつけたりして、いかにもタンゴらしい鋭い音を出します。 フォークやニュー・ミュージック系でよく出てくる8ビートですが、アクセントをしっかりつけるとノリのよい伴奏になります。ツ ツ チャ ツ ツ ツ チャ ツというパターンはよく現れます。このツ ツ チャ ツの最後のツのところでしっかりと音を小さくしないとツ ツ チャ チャになってしまってよいリズム感がでてきません。アクセントの場所は曲によっていろいろ変わります。チャ ツ チャ ツ チャ ツ チャ ツとかツ チャ ツ ツ ツ チャ ツ ツ、あるいはツ ツ チャ ツ ツ チャ ツ ツなどが出てきますが、これらのアクセントをしっかり使い分けられるようにして置きたいものです。 元気のよいパターンでは、8つ打ちの4つ目と5つ目がタイで結ばれ、チャ ツ ツ チャー ツ ツ ツ チャ ツ ツ チャー ツ ツ ツのようなのもあります。 16分音符のような細かな音が8小節や16小節のフレーズの切れ目の最後によく使われます。これは、ドラムがいないハーモニカ・バンドの場合に、ドラムが入れるべきフィル・インの代わりをコード・ハーモニカが担うためですが、このときは音楽用語でダブル・タンギングと呼ばれる舌を使った刻みが使われます。これは表記上よくTKTKと表されます。しかし文字どおりTKTKとやりますと、舌とハーモニカの距離が近すぎて、聴衆にTKTKという音がそのまま伝わってしまいます。 これは聞いているとかなり聞き苦しいもので、気を付けなければなりません。私は、どちらかといえばTAKATAKA的な感じで、舌を少し奥の方で上あごに接するようにして吹いたり、またスローな曲であれば極力ダブルタンギングを使わないでタタタタという感じの音をだすようにしています。安易にダブル・タンギングを使わないようにしましょう。(ただし、タタタタのような舌の速い動きはよく練習しないとなかなかきれいに出せませんね。) コード・ハーモニカはギターのリズム打ちの役目や、ドラムのフィルインの役目をします。これらの楽器は、あまり楽譜にとらわれずにかなり自由な打ち方をしますね。ポピュラーやジャズなどの演奏では、コード・ハーモニカも、楽譜に書いてあるからといってそのとおりにやろうと思わない方が生き生きとした伴奏になります。特にフィルインのパターンは毎回変えるくらいの気持ちを持ちましょう。プロのコード奏者の方が、「1回たりとも同じ伴奏をしたことはない。」と言い切っていらっしゃったのを覚えています。 ただし、他の方のリズムを崩してしまうのはよくありません。遊び心を持ちながらも、しっかりしたリズム感でもって伴奏するよう心がけましょう。 さて、コード・ハーモニカを吹くにあたっては、ぜひプロの演奏のレコードやCDを聞いてください。ハーモニキャッツ、ラバリヤーズ、トリオ・レズネーなどは古いレコードが多いので手に入りにくいかもしれませんが、アドラー・トリオ、ブルー・ハーモニキャッツ、ハーモニキャッツのベスト盤などはCDなので比較的手に入りやすいでしょう。メロディー、バス、コードの3人だけのアンサンブルですが、コードの活躍により、オーケストラルな迫力満点の音が作り出されています。これらの刻みを聞くことなしには決してコード・ハーモニカは上達しません。聞くことによって、文字では表せない多くのことを学び取ることができます。 Good Luck! ハーモニカ界ではコード・ハーモニカの認知度も向上し、長いハーモニカが出てきても驚かれることは少なくなりましたが、町内会、老人ホーム、デイケア・センターなどで演奏する機会も増えてきています。そのような、ハーモニカの認知度の低い場所では70cmもあるコード・ハーモニカは驚異の的です。楽器紹介で仕組みやコード打ちの役割を説明すると大変喜ばれます。説明と共にちょっとしたデモ演奏をしてあげるとさらに喜ばれます。 そこで、コード・ハーモニカを使ったいくつかの遊びを知っていると重宝します。いくつか紹介しましょう。 お辞儀 「起立−気を付け−礼−直れ」に使われるコード・パターンです。1箇所でできますから最も簡単な遊びです。 |
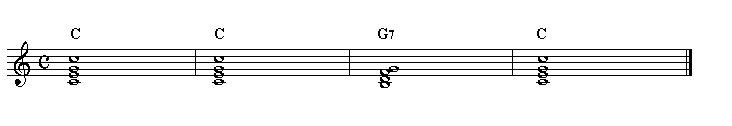
| パンパカパーン 「パンパカパーン・パ・パ・パ・パンパカパーン」のコード・パターンです。CとDbの距離が大きいので、大げさに身振りを加えて演奏しますと、大変受けます。ただし、かなりの練習が必要です。 |
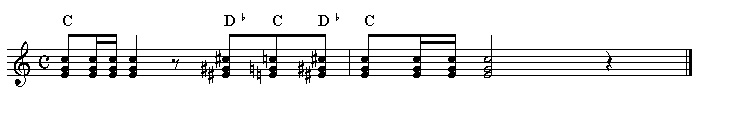
| オチ 話のオチで使われる「タン・タ・タ・ター・ター・ン・タン・タン」のパターンです。 |
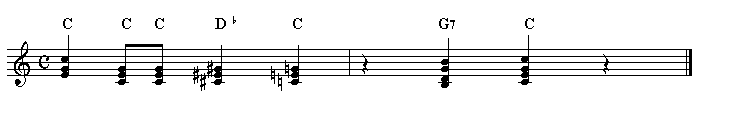
| サクラ 「サクラ」の出だしのメロディです。ラシドシのラとドのニュアンスを、Amの場所で少し位置を変えて表現します。 |
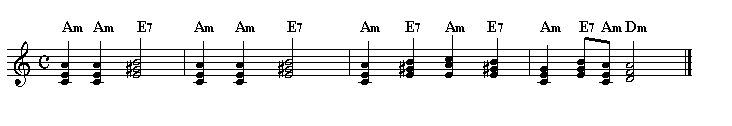
| コード・メロディ 最後の「サクラ」は、コード・ハーモにかでメロディを吹く例になっています。ハーモニキャッツのレコードやCDを聞いていますと、コードでメロディを吹く場面が時々出てきます。トリオは編成が単純なために、単調さを避けるためにコード・メロディやバス・メロディがよく使われています。 コード・メロディの極めつきはハーモニキャッツの「Peg O' My Heart(私のペギー)」でしょう。この演奏はミリオン・セラーになったと聞いております。他にも「It's a sin to tell a lie(嘘は罪)」、ラバリアーズの小粋なワルツ」などで華麗なコード・メロディを聴くことができます。 2002年アジア太平洋ハーモニカ・フェスティバルが厚木で開かれましたが、ゲスト出演したホット・ショッツのアル・スミスさんの吹くコード・ソロは驚異的です。お聞きになった方も多いと思います。ご自身でコードとバスの2重奏の楽譜集を出版していらっしゃいましたが、もう絶版ということで残念です。私自身、この曲集の「チム・チム・チェリー」を演奏したことがあります。 私の編曲の中にも「さらばベルリンの灯」では、コード・メロディを取り入れてみました。なかなかいい感じになります。 コードによるメロディは、ポジションが大きく跳ぶことが多いので、大変高度な技術となりますが、観客受けもよいので、ぜひ何曲かものにしておくとよいでしょう。 余談 なお、第4回アジア太平洋ハーモニカ大会で来日されたアドラー・トリオのドゥロア・アドラーさんが使ったコードハーモニカには、クロマチック・ハーモニカのようなスライド・レバーが付いています。レバーを押すことで、Maj7とm7のコードが吹けるようになっています。これらのコードは、ジャズやフォークの世界では必須で、とても重要なものです。アメリカのSPAHのデトロイト大会(1990年頃か)で、やはり今回来日されたハーモニカ・ホットショッツのアル・スミスさんと夜を徹して語らったときのアイデアを実現したものだそうです。アルさんも興味深く眺めておられました。 まだ試作品の段階なのでボディは金属で大変重く、予備がないので大切に使っているということでした。 |

目次へ
トップページへもどる |
お話へもどる |