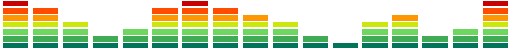
| クラシックを吹く理由
フレンドタウン17号(1999年6月)に掲載された記事です。 私は、ジャズ・ポピュラー系のハーモニカ奏者であると思っていますし、また思われています。しかし、最近何度かクラシックの曲を舞台で演奏しました。実は、この稿の表題は「クラシックを吹かなかった理由」でもよいのですが、肯定形を使って表現しました。 さて、なぜ最近までクラシックを吹かなかったのでしょう。それはズバリ難しかったからです。 大学時代、クロマチック・ハーモニカを購入した当時は、色々練習曲を探してクラシックの曲集を買いました。曲の中には、スラー、タイ、スタッカートなどの記号、pやmf、などの強弱記号、dimやaccelなどの速度記号などなど、曲の表現に関する指定がたくさん書いてあります。大学から音楽を始めた私には、これらの指定に気を配る余裕がまったくありませんでした。しかし、気を配らなければいけないのだということは理解していましたので、できない自分に腹が立つのです。一方、ジャズやポピュラーの曲集にはそれらがあまり書かれていません。自分で適当に解釈して吹いてよいのです。大学のクラブ内では合奏なので、多少いいかげんでもばれません。 そんなこんなで、30年近くクラシックは吹かないできました。 最近、楽器練習用のカラオケのCDが何枚か売り出されています。購入したフルート用のCDには、ポピュラーもクラシックも入っていました。中に「アルルの女より」メヌエットがあり、例のごとくスラーやスタッカートがたくさん含まれています。お手本のフルートを聞くと、見事にこれらを吹き分けています。 悔しいなと思って練習してみました。すると、さすがに30年前より余裕があり、なんとかこれらの記号をうまく吹き分けられました。また、横隔膜を使ったビブラートができるようになっていたこともあり、その曲らしい感じが出ていい雰囲気です。 それ以来です。クラシックの曲をレパートリに加えたのは。はやりのことばでいえば、30年前のリベンジでしょうか。 もうひとつの課題は、曲の暗譜演奏です。単にメロディだけでなく、これらの記号の吹き分けも含めて暗譜するのは、また一段と難しく感じます。残念ながら、まだ演奏会で暗譜で演奏できていません。いつかチャレンジしたいと思います。 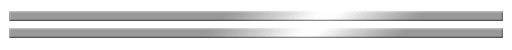 これまでに聴衆の前で演奏したクラシック曲目 |
トップページへもどる |
お話へもどる |