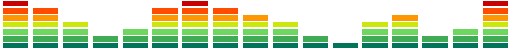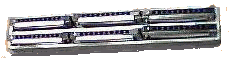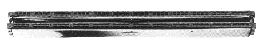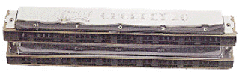| 手作りコード・ハーモニカAhda Chorda 未発表(2001/6/16記) ハーモニカ・バンド「ハミング・キャッツ」では、手作りのコード・ハーモニカ、アーダコーダ(Ahda Chorda)が活躍しています。これは、10ホールズ・ダイアトニック・ハーモニカが和音を出せることを利用して、6本のハーモニカを木の枠で束ねたものです。中々便利なもので、教室の練習で使うと共に、ステージでも使っています。「あれは何だ、初めて見た。」などの声も聞かれるので、これの原理を紹介しておきましょう。
吹き: C E G C E G C E G C 吸い: D G B D F A B D F A それで、4つ、5つの音を大きく咥えて吹くとどこでも和音としては ド ミ ソ ド、すなわちCメジャーの和音になります。また同様に左端を大きく咥えて吸うと、ソ シ レ ファ、すなわちG7の和音になります。つまり、1本でCとG7のコードを出せるわけです。これはC調のハーモニカでしたから、同様に考えるとF調のハーモニカではFとC7の和音、G調のハーモニカではGとD7の和音が出せることがわかります。 次にAマイナーのダイアトニック・ハーモニカの音の並び方は、次のようになっています。 吹き:A C E A C E A C E A 吸い:B E G# B D F G# B D F 吹いた時の和音はどこでも ラ ド ミ ラ、すなわちAマイナーの和音、左端を吸ったときの和音は ミ #ソ シ レ、すなわちE7の和音になります。つまり、1本でAmとE7のコードが出せるわけです。 このようにダイアトニック・ハーモニカがきれいな和音が出せることに注目して作ったのがアーダコーダです。命名の由来は、あーでもない、こーでもないと考えていて、いっそ「アーダコーダ」にしようという単純なものです。Hohner社のコード・ハーモニカ「アコーダ(Accorda)」と似てもいます。 木枠を手作りし、ハーモニカを並べます。並べ方は、基本系は次のようにします。
これは、次のアコーダの配列に似ていて、色付き部分を取り出した形になっています。大きな違いは、Cコードの下がCmではなくAmになっていることと、マイナー・コードの部分を吸ったときに出るディミニッシュやオーギュメントのコードがなく、代わりに例えばAmを吸うとE7が出るということです。
では、「アーダコーダ」で出せる和音を図示してみます。
これらの和音でどれだけのことができるか考えてみましょう。 C調(ハ調調)の主要3和音はC、F、G7ですから下の色付き部分で間に合います。
同様に、Am(イ短調)の主要3和音はAm、Dm、E7ですから、下の色付き部分で間に合います。
また、フォークソングや歌謡曲で循環コードが使われている場合、C、Am、Dm、G7がよく出てきます。これも下の色付き部分で十分です。
つまり、調子記号のついていない調子であれば、左の2列で必要な和音はこと足りるということです。アコーダではAmはCよりも3列右にありますから、かなり大きなハーモニカの動きが必要となります。その点アーダコーダの方が初心者向けには便利です。Hohner社のVinetaも2本持つ場合にはこのような組み合せが可能です。中国製コード・ハーモニカ、Huang社のChordet 20はこれとよく似た配列をしていますが、Amを吸うとEdimが出るようになっていて、循環コード系の曲は伴奏できません。
次に#記号が一つ付いた調子、G調(ト調調)またはEm調(ホ短調)の場合には、コード体系が右に一つ平行移動するというのはアコーダもアーダコーダもChordet 20も同じ概念ですから、右の2列があれば十分です。
それでは、b記号が一つのF調(へ長調)またはDm調(ニ短調)の時はどうでしょうか。アコーダやChordet 20では左へ1列移動するだけですみますね。この場合、アーダコーダではハーモニカを入れ替えて左へ1列移動させるという技が使えます。
Vinetaではこの場合、適当なハーモニカの組み合わせが作れないので大変困ります。アーダコーダの場合、基本的にどの調子でも主要3和音や循環コード系の範囲ならばこのハーモニカを入れ替えるという技で対処できます。 しかし、練習時や本番のステージ上で6本ハーモニカを入れ替えるのは煩雑なものです。アーダコーダの場合、もっと簡単な対処法があります。たとえばF調の場合にはGやEmが使われることが少ないので、この2本だけをそれぞれBbとGmに入れ替えるのです。
ちょっと変則的な配列になりますが、それほど混乱することはありません。 ステージで発表する曲にこれら6本全部が使われて、まだ足りない場合もあります。ハミングキャッツのレパートリである「ロミオとジュリエット」のコード進行は、次のようなものです。 Em |F |Em |Dm |Am |C |F |Dm | Em |Am |Am Em|Bb |F |Em |Am また、他の曲はG調を含んでいます。このようなときは、曲毎にハーモニカを入れ替えるのではなくてもう1本Bbのハーモニカを指の間にはさむことで対処することができます。
まれに、Gaugのような特殊な和音がどうしても欲しい場合が出てきます。たとえば、「浜辺の歌」ではGaugはなくてはならない和音です。私は、Gのハーモニカのリードを削ってGaugに仕立てたものを用意しておき、不要なハーモニカを入れ替えたり、指の間にはさんだりして、本来ならばないはずの和音を出したりします。 アーダコーダの特徴の一つに、メロディも吹けるということがあります。元々それぞれが10ホールズ・ダイアトニック・ハーモニカなのですから、場合によってはメロディを吹けばよいのです。これは、他のコード・ハーモニカにはできない芸当といってよいでしょう。10ホールとしてのベンドも可能ですから、私はときどきブルース・プレイヤーとジャム・セッションしたりします。伴奏に回ったり、アドリブしたりと中々面白いものです。 このように、アーダコーダは工夫次第で色々な曲の伴奏に使えます。入れ替えが効くことから、VinetaやChordet 20よりも応用範囲が広いといえます。 もちろんアコーダを使えば問題は解消するのですが、アコーダには大きい、重いといった問題点があります。会社から練習場に直行する場合など、普通の鞄に楽々収まるアーダコーダはとても重宝します。皆さんも一本作ってみられたらいかがでしょうか。 |